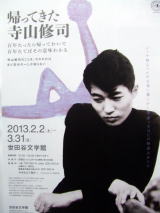寺山修司
【ブログ掲載:2013年3月31日〜4月21日】
▼先日、芦花公園の近くにある世田谷文学館に行った。「帰ってきた寺山修司」と題する企画展をやっていたからである。入り口に貼り出されたポスターには、「百年たったら帰っておいで 百年たったらその意味わかる」という彼のアフォリズムが、添えられていた。
寺山修司が亡くなってから、今年で丁度30年になる。
彼は歌人であり、アフォリズムをちりばめた詩や評論を書いた。ラジオドラマや芝居の脚本を書き、それに飽き足らずに劇団を主宰し、映画を撮り、小説を書き、競馬の予想コラムも書いた。
筆者は寺山修司のあまり良い読者ではなく、芝居の愛好家でもなかったが、彼の言動には人並みの関心を懐いていた。彼が47歳で亡くなり、最期まで病床で自分の書いたものに手を入れていたと聞いたときは、静かな衝撃があった。
長いあいだ寺山は、気になる存在だった。
▼寺山修司は昭和10年青森県三沢市の生まれである。警察官だった父親は戦地から帰らず、母親は三沢の米軍基地で働き、さらに九州の米軍基地へ移動した。寺山は母と別れ、青森市の親戚の家で中学、高校時代を過ごす。
中学生の時、同級だった京武久美の影響で俳句を創りはじめる。寺山と京武は同じ青森高校に進学し、ともに文芸部に所属して俳句を作り続けた。受験雑誌や地元新聞の俳句投稿欄の常連となり、高校3年の時には全国の高校生に呼びかけて俳句雑誌「牧羊神」を創刊した。
昭和29年、親戚の援助により早稲田大学に進学。「短歌研究」誌の第1回新人賞で特選となった中条ふみ子の短歌に刺激を受け、この夏、第2回の新人賞に応募。寺山の五十首詠「チエホフ祭」は第1位に選ばれた。
しかしその冬、ネフローゼを発病し、生活保護法を受けて入院。以来3年間、闘病生活を強いられた。
昭和33年に歌集『空には本』を出版。
谷川俊太郎の勧めでラジオドラマを書きはじめ、また戯曲や映画シナリオを書くようになる。
▼寺山修司にとって「チエホフ祭」の新人賞受賞は、歌人としての出発点であるとともに、その才能が世の中に広く知られるきっかけとなった出来事だったが、受賞後しばらくして厳しい批判に直面した。それらの歌が他人の句の模倣や焼き直しではないか、という批判の声が、俳句界、短歌界から上がったからである。たとえば寺山の短歌
莨火を床に踏み消して立ちあがるチエホフ祭の若き俳優
は、中村草田男の句「蜀の火を莨火としつチエホフ忌」の模倣であり、
向日葵の下に饒舌高きかな人を訪はずば自己なき男
は、同じく中村草田男の句「ひとを訪はずば自己なき男月見草」の模倣だという非難である。
俳人・楠本健吉は、「俳句、短歌自由自在のアレンジの手腕の妙、その精神の堕落ぶりにはまったく恐れ入ったのであった」と書いた。
『虚人 寺山修司伝』(田澤拓也)に拠れば、「チエホフ祭」には寺山自身の俳句や京武久美の俳句もいくつか、短歌に改作されて入っていた。
寺山の句「桃太る夜は怒りを詩にこめて」は、
桃太る夜はひそかな小市民の怒りをこめしわが無名の詩
となり、同じく寺山の「わが夏帽どこまで転べども故郷」は、
ころがりしカンカン帽を追うごとく故郷の道を駆けて帰らむ
となった。
京武久美の句「メーデー歌薄き帽子に髪あまる」は、
啄木祭のビラ貼りに来し女子大生の古きベレーに黒髪あまる
という短歌に改作された。
さらに言えば、寺山の「桃太る夜」の俳句自体、西東三鬼の「中年や遠くみのれる夜の桃」を下敷きにしていることは、指摘されれば誰しも気がつくところだろう。
▼寺山修司の短歌をめぐる騒ぎからすでに60年近い年月が経った現在、寺山の「模倣」を批判する声は聞こえない。
過去の事件として「模倣」問題を取り上げるときも、多くの論者は、「本歌取り」や「本句取り」はもともと和歌や俳句の伝統であり、常套手段にほかならないと、肯定的に扱う。そして「模倣」したかどうか、「借用」したかどうかということよりも、その模倣や借用の結果、どのように瑞々しい新しい歌を生み出したか、に重点を置いて受け止め、考えようとする。
寺山の新人賞受賞当時からの良き理解者・塚本邦雄は、次のように書いた。
《「チエホフ祭」の中のこれら人口に膾炙した作品は、記憶の中でも常に剪りたての花、摘んだばかりの果実のやうにみづみづしい。(中略)原典を自家薬籠中のものとして自在に操り、藍より出た青より冴冴と生まれ変らせる、この本歌取りの巧妙さ。新古今あたりのそれの厳粛な繁文縟礼めいた修辞学を、微笑と共に跳び越えてこれらの作品は輝いてゐる。》(『麒麟騎手――寺山修司論――』新書館 1974年)
塚本が「これらの作品」として挙げたのは、前回挙げた「莨火を」の歌のほか、
蛮声をあげて九月の森に入れりハイネのために学をあざむき
向日葵は枯れつつ花を捧げをり父の墓標はわれより低し
一粒の向日葵の種まきしのみに荒野をわれの処女地と呼びき などである。
寺山の歌集『空には本』には、彼の代表作と目される次の歌も納められている。
マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや
この歌にも元になった俳句が指摘されている。冨澤赤黄男(かきお 1902−1962)の句
「一本のマッチをすれば湖は霧」であり、「めつむれば祖国は蒼き海の上」である。
たしかに「マッチ擦る」も「海」も「霧」も「祖国」も、冨澤の句からの借用であることは明らかだ。しかし「身を捨つるほどの祖国」と芯を入れることで、上句と下句を統一し、全体を引き締め、見事にひとつの歌としてまとめ上げたのは寺山である。寺山の歌は借用元の俳句を、十分越えていると見るべきだろう。
山口瞳は「この歌には我等戦中派の無念が集約され結晶しているように思われる。調べも上等だ。」と称賛したという。自分たちが賭けた祖国は失われ、いま身を投じるに足る祖国などどこにもないではないか、という無念さである。
しかしそれでは寺山は、戦中派の「無念さ」を自分自身の「無念さ」としてこの歌を詠んだのだろうか。
▼寺山は『空には本』を昭和33年に出したあと、昭和37年に第二歌集『血と麦』、昭和40年に第三歌集『田園に死す』を発表している。寺山の短歌創作の秘密を覗くために、彼の歌をよく知られたものを中心に、いくつか見てみよう。
そら豆の殻一せいに鳴る夕母につながるわれのソネット(空には本)
とびやすき葡萄の汁で汚すなかれ虐げられし少年の詩を(〃)
吊るされて玉葱芽ぐむ納屋ふかくツルゲーネフをはじめて読みき(〃)
海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり(〃)
すでに亡き父への葉書一枚もち冬田を越えて來し郵便夫(血と麦)
乾葡萄喉より舌へかみもどし父となりたしあるときふいに(〃)
剥製の鷹ひっそりと冷えている夜なりひとり海見にゆかん(〃)
大工町寺町米町仏町老母買ふ町あらずやつばめよ(田園に死す)
新しき仏壇買ひに行きしまま行方不明のおとうとと鳥(〃)
地平線縫ひ閉ぢむため針箱に姉がかくしておきし絹針(〃)
亡き母の真赤な櫛で梳きやれば山鳩の羽毛抜けやまぬなり(〃)
寺山修司の短歌の特徴のひとつは、その分かりやすさにある。表現が分かりやすいことに加え、情景が鮮やかに読み手の脳裏に像を結ぶからである。
中には上に挙げた「剥製の鷹」の歌のように、一見、上句と下句の論理のつながりが見えにくいものある。しかし口ずさんでみれば、読み手は上句と下句が無理なく、そして見事に連結していることを発見する。死んだ鷹の剥製の置かれた夜の冷たさと、「ひとり海を見にゆかん」という熱い意志や行動が支配する生きる者の世界。その対比の深さの中で、「飛躍」と「連結」が一つの絵として心地よく納得されるからである。
二つめの特徴は、あえて誤解を招く言い方をするなら、これらの歌が寺山の「思い」を詠んだものではないということだろう。
筆者の考えでは、寺山は自分の「生活」を歌わなかったし、現実の光景を詠まなかった。機知や知識を誇ったり、技巧に遊ぶこともしなかった。そのかわり「絵になる情景」を想い描き、それを歌い上げることに全力を投入した。
「一枚の絵」を描きだすために言葉を選び貼り付ける作業こそ、寺山の短歌創作だった。
▼歌を詠むとき、誰しも一つの光景を設定する。それを描くために言葉を選び、言葉の力を駆使するのが、全ての歌人の営みである。
歌おうとする光景は多くの場合、詠み手の生活や体験に根ざすものである。自分の感動や感傷、喜怒哀楽に至るもろもろの思いを盛るに足る情景は、直接の体験の中に求めるのがもっとも容易であるからだ。
しかし寺山の場合、自分の直接の生活体験に取材することは少なく、生活体験を歌うことを自らに禁じていたようにみえる。その代わり、書物で読んだ光景や他人が歌や俳句に詠んだ光景をもとに、人工的に情景をこしらえるのが寺山の「方法」だった。
もちろん、少女の前に麦藁帽子をかぶった少年の寺山が立つ光景や、亡き父親あての葉書が届けられる光景が、実体験なのか想像によるものなのかは、いずれとも解せる。玉葱の吊るされた納屋で読む本は、シェークスピアやモーパッサンではなく、「初恋」のロシア人作家・ツルゲーネフでなければならないが、それが寺山自身の体験と重なるのかどうかは判らない。
しかし第三歌集『田園に死す』になると、寺山が実体験に拠るのではなく、言葉のコラージュによって人工的な光景を創りだしていることが、明瞭になる。
仏壇、柱時計、針箱と絹針、真赤な櫛、間引き、義眼、斧、縄、法医学など、北国の暗い風土を舞台に禍々しく怪しげな小道具が並べられ、極彩色のおどろおどろしい世界が生み出される。不吉にして瑞々しい光景を創りだすために、生きている母は亡くなったことになり、存在しない弟や姉が登場する。
『田園に死す』から、さらにいくつか引用する。
売りに行く柱時計がふいに鳴る横抱きにして枯野ゆくとき(田園に死す)
間引かれしゆゑに一生欠席する学校地獄のおとうとの椅子(〃)
たった一つの嫁入道具の仏壇を義眼のうつるまで磨くなり(〃)
中古の斧買ひにゆく母のため長子は学びをり法医学(〃)
いまだ首吊らざりし縄たばねられ背後の壁に古びつつあり(〃)
売られたる夜の冬田へ一人来て埋めゆく母の真赤な櫛を(〃)
トラホーム洗ひし水を捨てにゆく真赤な椿咲くところまで(〃)
見るために両瞼をふかく裂かんとす剃刀の刃に地平をうつし(〃)
くくられて村を出てゆくものが見ゆ鶏の血いろにスカーフを巻き(〃)
▼『田園に死す』で明瞭になった寺山の「方法」は、初期の歌に遡るといってよいだろう。寺山修司にとっては、歌が見事な情景を描き出すかどうかが問題のすべてであり、それが実体験を土台とした自分の「思い」であるかどうかは、まったく問題ではなかった。
一幅の絵としておさまるかどうか、世界の割れ目を一瞬垣間見せる情景であるかどうか、それだけが寺山の関心事であり、それを彼は確かな腕で組みたててみせた。
寺山にとって書物こそ彼の経験であり、他人の歌や句からの借用や模倣は必須であり、必然だった。
「やまとうたは ひとの心を種として よろずの言の葉とぞなれりける」はずなのだが、寺山の場合、「よろずの言の葉」から成る光景がまずあり、種となるべき自分の心は、表立って歌われるべきものではなかったのだ。
寺山はどこかで、自分が書くのは自分を語るためではなく、自分を語らないため、自分を隠すためだ、というようなことを語っていなかったか?
寺山の歌には、彼の生活の現実であった貧困や絶対安静を命じられた闘病生活は出てこない。父や母の不在はたびたび歌の素材として使われるが、彼の孤独感が直接歌われることはない。
徹底して自分の生活体験や思いを歌わないこと、徹底した虚構への執着、―――模倣を批判された寺山修司の独創性はそこにこそあった。
上のように考えるなら、「マッチ擦る」の歌も、戦中派の無念に共感して詠んだと捉えることは難しい。「海に霧深し」の句に、「祖国の行く末を見通せぬ不安」を読み取るのも、作者の社会性を買い被ることになるだろう。
▼世田谷文学館の展示では、「寺山修司の短歌の森」という部屋がつくられていた。暗い部屋の中に、寺山の歌を書いた大きな短冊が20〜30枚天井から吊るされ、短冊には照明が当たり、それを読み上げる寺山自身の東北なまりの声が、三味線の音とともに流されていた。生前、何かの折に録音したものだろうが、それを活かしたなかなか良い企画だった。
寺山の歌は中学校の国語教科書にも載っていると、展示の中で紹介されていた。
ころがりしカンカン帽を追うごとく故郷の道を駆けて帰らむ
海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり
など、たしかに子どもたちが愛唱するのにふさわしい歌であろう。
▼前回、寺山修司の短歌の特徴は、自分の生活体験や思いを歌わないことにあると述べ、徹底した虚構への執着にこそ寺山修司の独創性はある、と書いた。
それは彼の短歌に留まるものではない。彼の創りだす芝居やドラマの台本では、世界が虚構であるだけでなく、「意味」は迷路に迷い込み、「現実」は重みを持たずに浮遊し、あからさまな「非現実」が賑やかに囃される。
しかしひとつだけ、寺山の私生活がそのまま使われた台本がある。「母がひとりで挽くコーヒー挽き機械」という30分のテレビドラマである。
主要な登場人物は2人、母親と息子である。息子は21歳で同じ齢の妻といっしょに暮らし、母親はひとりで別のアパートに住んでいる。日曜日の午後、息子はいつものように母親を訪ねる。
母親は嫁を嫌っており、息子と二人で暮らしたいと願っている。妻と母親のあいだに立たされる息子は、コーヒーを淹れながら母親の愚痴を聞かされる。息子は、母ちゃんも友だちを作ればいいんだ、と言う。
――友だち?
――そう。
母親は前の週に、間違いハガキが届いたという話をする。よく見ると、向かいのアパートに住む若い女性宛てのもので、感じのよさそうな人なので、持っていけば、それがきっかけで話をする仲になるかもしれないと考えた。次の日は早く起きて、悪い感じを与えないようによそ行きのワンピースを着て、向かいのアパートの前まで行ったんだけどね。――
――どうしたの?
――ハガキ一枚持って、いい歳したおばあちゃんが化粧して訪問着来ていくのも、何となく大げさで、かえって笑われるかもしれないし、アパートの前を行ったり来たりしながらいろいろ考えて、けっきょく郵便受けに入れてきてしまった。
――馬鹿だなあ。
――帰って来てこのベッドに腰を下ろしたら、母ちゃんさみしくってね、泣けてきてしょうがなかったよ。
息子は母親に、嫁といっしょに3人で暮すことを提案するが、母親は激しく拒否する。あんな女,誰が認めるものか。おまえはあたしの子だよ、あたしが生んだ、あたしの息子なんだよ――。
息子は帰り際に、靴を履いてから振り向いて言う。
――ひとつだけ頼みがあるんだ。……夜、俺のアパートを見に来るのはやめて欲しいんだ。毎晩あんなところに立って、二階を見上げられるのは困るんだよ、いろいろと。あんなところから、俺たちが電気消すまで毎晩毎晩じっと見てられると……。
母親、ふいに泣き出す。
息子は「じゃあ、また」と、快活を装って出て行く。
▼寺山の元妻であり、離婚したあとも寺山が亡くなるまで共に「演劇実験室・天井桟敷」を運営していた九條映子(今日子)によれば、上のドラマには彼ら夫婦と寺山の母の関係が、そのままとりあげられている。
寺山の母親はつは、寺山と九條の結婚に反対した。「うちの修ちゃんはまだ子供です。結婚しても恥ずかしくないように、私がこれから育てなければなりません。結婚はそれまでしばらく待ってください。」
母親は結婚式に出席せず、式は仲人役の谷川俊太郎と九條の家族だけで行われた。寺山は当時母親と住んでいた四谷のアパートから、家出するように永福町の新居に移った。
深夜、ふたりがベッドに入ると、雨戸に石が当たる音がする。明かりをつけようと伸ばした九條の手を抑えて、寺山が「じっとしていよう、そのうち帰るから」と言った。母親の「夜の来襲」は、ふたりの寝る時間を見計らったように、それから何日かおきに続いた。
ある夜、2時を過ぎたころ、ふたりは白い煙で目が覚める。台所の外に落ちていた焼け焦げた布をつまみあげて寺山は、これは病院で自分が着ていた浴衣だと言った。(九條今日子『ムッシュウ・寺山修司』ちくま文庫 1993年)
母親の寺山はつは、ふたりの結婚について、九條の両親が三人で暮らすことに反対した、だから自分もその結婚に反対だった、と書いている。(寺山はつ『母の蛍』新書館 1985年)。しかしそれは事実ではないだろう。深夜に息子の新居を襲うような妄執のエネルギーは、息子を取り返したい、取られたくない、という理性を超えた欲望や自衛本能に深く根ざしているのであり、理屈で説明のつくものではないからだ。
虚構への執着を徹底して自分に課していた寺山修司が、私小説作家も裸足で逃げだすような「私ドラマ」の台本をなぜ書いたのか、大きな謎であるが、母親の妄執のエネルギーの凄さが寺山に、虚構に昇華するゆとりを与えなかったのかもしれない。
▼『虚人 寺山修司伝』は、寺山の故郷の多くの関係者に取材している。
寺山はその「自伝」で語るのとは逆に苛められっ子であり、運動がまったく苦手で、後に掲げたスローガン「書を捨てよ、町へ出よう」とは逆に、「家にこもって本を読もう」というタイプだったという。負けず嫌いで自惚れ屋、自己顕示欲の強い少年だった、という仲間の声も収めている。
寺山の中学・高校の同級生・京武久美は、次のように著者に語った。「寺山の俳句や短歌は自分を売り出すための手段だと私は思っているの。短歌で一応名を売れば、何も短歌にいつまでもしがみついている必要はない、ということだと思う。後年の彼の転身は、結局、俳句でも短歌でもそれだけでは食えないということなんです。彼は食うことが最終的な目的だったろうと思うのです。」
また九條映子は寺山との生活を伝え、大食漢だが酒が飲めず、大工仕事ができず、電球ひとつ換えられなかった、と語っている。
しかしそういう「実像」をいくら集めても、「寺山修司」の像はそこを容易にすり抜け、拡がる。虚実のあいだに捉えがたく拡がる言葉の迷路の魅力は、死後30年を経た現在も色あせていない。
▼寺山の絶筆は、週刊誌に掲載されたエッセー「墓場まで何マイル?」である。
パリの古本屋で買ったお墓の写真集のことから話は始まり、次のように締めくくられる。
《私は肝硬変で死ぬだろう。そのことだけは、はっきりしている。だが、だからと言って墓は建てて欲しくない。私の墓は、私のことばであれば、充分。》
そしてそのあとにウイリアム・サローヤンのことばが引用されて、エッセーは終わる。
「あらゆる男は、命をもらった死である。もらった命に名誉を与えること。それだけが、男にとって宿命と名づけられる。」
ARCHIVESに戻る