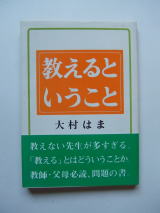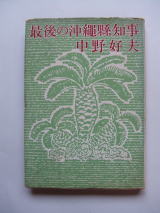『教えるということ』 大村はま
共文社 昭和48年刊
【ブログ掲載:2011年12月17日〜12月31日】
1.
「教育」について発言するのを、躊躇する気持ちがある。
それはひとつには、きわめて容易なことだからだ。誰しも自分の体験を振り返り、その記憶を基準にして何らかの感想や意見らしきものを述べることができる。
もう一つの理由は、それが困難なことだからだ。語ることと実現することのあいだに大きな距離のある教育という事業について、教育現場の具体的な事情や事実を知らない部外者が気楽に発言することは、なんとなく畏れ多いという気持ちが強かった。
だが、ときどき報じられる教育関係のニュースを耳にするとき、違和感を覚えることも少なくなかった。とくに教育関係者のあいだで語られる言葉、たとえば「子どもたちの眼の高さ」で話すことが大事だとか、「いのちの大切さを教える教育」などという過度に情緒的な言葉は、学校と社会の落差を示しているように思えた。
2.
『教えるということ』の著者・大村はまは、1906年(明治39年)生れの国語の教師である。戦前は長野と東京の高等女学校で教え、戦後は都内各地の新制中学校の教壇に立った。国語教育で優れた業績を上げたとして、東京都教育功労賞、ペスタロッチ賞等を受賞している。
『教えるということ』は、新任の若い教師を対象にした講演や教師の研修会で話したことなど、三つの講演の記録である。国語教育の話題にとどまらず、自分の教師生活を振り返りながら、教育や教師の仕事一般について語っている。内容は平易、常識的で、目新しい主張もないように思えるが、おそらくそうではない。戦後の教育界の潮流から見て、きわめて厳しい指摘が大村によってなされている、と読むべきなのだと後になって気づいたのだが、とりあえず大村の言葉をいくつか引用しよう。
《………子どもがかわいいという目つきで見たり、かわいいという言葉をかけてやったり、いっしょに遊んでやったりしたとしても、そんなことは、たわいもないことだと思うんです。いっしょに遊んでやれば、子どもと同じ世界におられるなんて考えるのは、あまりに安易にすぎませんか。そうじゃないんです。もっともっと大事なことは、(教師が)研究していて、勉強の苦しみと喜びとをひしひしと、日に日に感じていること、そして、伸びたい希望が胸にあふれていることです。》
《子どもがひとりで生き抜くために、どれだけの力があったらよいか、それを鍛えぬこうとするのが、それが先生の愛情だと思いますし、ほんとに鍛えぬく実力が先生の技術だと思います。》
大村によれば、子どもとは、伸びたくて伸びたくてたまらない人、「身の程知らずに伸びたい人」のことである。だから、つねに研究を怠らず、自分も伸びたいと努力している教師だけが、子どもと同じ世界にいることができる。
教師の研究は、教える技術に関してである。作文を書けなくて悩んでいる子がいれば、書き出しを書いてやって、その先を書いてごらん、と導いてやったらどうか。途中で行き詰った子どもには、そこで何を見たの?それは何の木なの?と助け舟を出せば、文章を先に進めることができるだろう。それが「書くことを教える」ことなのに、教えることをしない教師が多すぎる。
《………小学生や中学生の段階で、個性が傷つくなんてしゃれたことを言うのはおかしいことです。そんなことよりも、書けない子どもがたくさんいて、先生が来て何とかしてくれるのを無意識に、しかし、心から待っているのです。》
3.
大村の「教え方」を、もう少し見てみよう。
大村から区立中学校で教えを受けた刈谷夏子は、後に大村と対談の場を持ち、大村の国語教育についてあれこれ尋ね、また自分の受けた授業を思い出している。(『教えることの復権』 大村はま、刈谷剛彦、刈谷夏子 2003年 筑摩書房刊)
刈谷夏子が、大村教室で学んだ大切なことのひとつは、話し合いについての基礎を学んだことだ、と話を向けると、大村は、戦争のあと呆然となり、そして新しい民主的な国をつくるために、中学校の教師として「きちんと役に立つ国語教育を本気でやっていこうと決めた」と言う。そのとき大きな目標となるのが、話す力、話し合う力を育てることだった。
《今の時代に、国語の先生で、話し合いをやらせない先生なんていません。(中略)でも、いけないのは、話し合いを教えていないということ。》
大村は、話し合いの前にまず教材を用意する。生徒がみな発言できる状態にもっていくために、その教材が使われる。
たとえば、少年駅伝夫が主人公の短い物語を生徒に読ませ、その少年がどういう人間であるか、20字以内の言葉で表現し、副題を付けさせる。クラスの人数分の副題が出てきたところで、どれが主人公をよく表現しているか、どれが優れているかを考え、推薦する副題とその理由をはっきり持たせる。そこまで準備してから、話し合いに入る。
話し合いの中では、事実と違うものを省き、人を引き付けるところのないものを省き、目立つもの、表現として優れたものを選んでいくが、ひとつに絞ることが目的ではない。選ぶための話し合いの中で、生徒たちに話し合いの技術を学ばせることが目的であり、そのために大村は、自分で話し合いの場に加わり、手本を見せた。
《たとえば夏子さんが司会をしていてつっかえてしまったとしても、励ましたりしない。自分(大村)が司会者になってすっと入って続けるわけ。そうするとああいうことを言えばいいのかと思って、具体的なことばを覚えるでしょう。そして話し合いがちゃんと動くようになったら私は目立たないように、すうっと下がってしまう。》
《話し手の一人になって、あの子になったりこの子になったりして発言していく。みんなそれぞれに、ああそうかとか、それじゃこんな発言をするとか、生きた見本に学びつつ教わりつつ……という状態になって、話し合いも進み子どもも伸びる。》
刈谷夏子は、当時の授業を思い出して次のように言う。
《先生にこうすればよかったという方向を見せてもらった時に、ほんとになにかわかった気持がする。ああ言えばよかったのかって、さっきまでことばに詰まっていた本人が、それはいちばんよく分かる。もやもやしていて、出そうで出てこなかったこととか、出口が見つからないで困っていたようなとき、その思いがナマな時に先生に助け舟を出してもらうと、深く納得できるんですよね。そのタイミングをよく見ていらした。》
大村はタイミングよく助け舟を出すために、生徒の一人一人を思い浮かべながら、事前にいくつもの「脚本」を書いて用意したという。
《話し合いを指導するということは容易ならぬことですよ。それなのに、話し合いというのは先生が楽をする時間で、お気楽に「では互いに話し合ってください」なんて平気な顔をして言うでしょ。それではまったく教えたことにはならない。》
刈谷が「本気で瞬間瞬間の流れを読んで対応しようと思ったら、もう必死でしょうね。」というと、大村は「そう。だから話し合い指導は一日に何回もはとてもやれませんでしたよ。ほんとうに疲れてしまって。」と答えている。
大村はまの言う「教えるということ」がどのような質のものであるかをよく示す、エピソードだといえるだろう。
4.
大村はまの教育に対する考え方は、単純明快な太い線で貫かれている。
教育とは、子どもたちに生きていく力を身につけさせることであり、学校とは子どもたちが大人になるために、ひとに頼らず自分で判断することを学ぶところである。
教師はそのために「教える技術」を磨かなければならないのであり、教える専門職としての技術を持ってはじめて一人前の社会人として胸を張れる、という。
一般社会から見れば常識的な大村の主張であるが、彼女があえて講演でこう語ったということは、講演のあった1970年当時の「教育界」に、こうした考えに反する現実や考え方が広がっていたことを意味するのだろう。
筆者はそのあたりの事情にまるで暗いのだが、80年代後半から90年代に、「いじめ」や「学級崩壊」などの教育問題が社会の注目を集め出すと、「教育界」内部の議論も外部に知られるようになった。その中には、小首をかしげざるをえないような話がいくつもあった。
5.
「教師は知識を教え込む指導者ではなく、児童生徒の学習の支援者であるべきだ。」
そういう考え方が教育現場に浸透し、教師たちは「教える」ことを躊躇し、子どもたちの学力低下が進んでいる、というような話が、ひところあった。
そして、そういう教育現場の変化の前提には、「学力」というものを単なる知識の量としてではなく、自ら学び自ら考える力としてとらえなおすという、「学力観」の変化があると説明された。
この、自ら学び自ら考える力は「生きる力」とも呼ばれ、それを育むための「体験学習」や「総合的な学習」が提唱された。
生徒の学習成績についても、「関心、意欲、態度」を評価することが大事だとされ、教室で手をあげた回数がモノをいうのだと、まことしやかに囁かれた。
こういう「教育改革」は、たとえば次のような「考え」に後押しされていたのだろう。
《……知識の暗記量を増やそうとする考え方はIT時代にふさわしくない。知識や情報はコンピュータによって大量かつ豊かに瞬時に手許に届く時代である。したがって、今後は、問題解決能力こそ学校が目指すべき学力の内容であるべきである。社会をめぐり、自然をめぐり、自分自身をめぐって、子どもたちはいろいろな問題に興味をもっているに違いない。さらに、人類は世界のグローバル化に伴って、かって当面したことのない新たな困難な問題を解決していかなければならない。まさに、環境問題、国際問題、情報化に伴う問題に代表される困難な問題を創造的に解決していく力を育てて行くことこそ、今後の学校教育の最大の目的である。すなわち、子どもたちは、グローバル社会における「地球市民」として「生きて」行かねばならないはずである。》 (『学力低下論批判』加藤幸次・高浦勝義編著 黎明書房 2001年)
率直に問題意識を述べている点だけは評価したいが、その内容は「教育改革」の根拠の浅さを露呈しているといえる。社会が新しい困難な問題に直面しているということが、なぜただちに子供たちの基礎教育を変える理由、それも教育内容ではなく「教育」に対する基本的考え方を変える理由になるのか。
また、子どもたちが自ら学び自ら考え、問題を解決する力を身につけることと、子どもたちの知識を増やし、「読み書き算盤」の基礎的トレーニングを課すことを、なぜ対立的にとらえなければならないのか。
漠然とした既成観念に寄りかかりながら、「IT時代」や「グローバル化」や「地球市民」という言葉が空しく躍っている。こういう千鳥足の文章が通用するとすれば、教育という業界も甘いところだと言わなければならないが、皮肉はひとまず控えよう。
前回述べたように大村はまは、生徒たちに「生きていく力」をつけるには言葉の力を身につけさせなければならないと考え、使命感に燃え、「教えること」に打ち込んだ。
一方、「新しい学力観」の下で、子どもたちに「生きる力」をつけるために、教師たちは「教えること」から後退し、学習の「支援者」として子供たちの可能性を見守ることを期待された。
この喜劇的な落差は、何を象徴しているのだろうか。
6.
2か月ほど前の新聞(朝日)のコラムに、××小学校では毎年沖縄に修学旅行し、「いのちの大切さを学ぶ」学習を行っている、という記事があった。
どのような学習をしたのか、具体的に読んだ記憶はなく、記事も手元に無いので確かめられないのだが、おそらく戦跡を見学したり、高齢の戦争体験者から悲惨な体験談を聞いたりしたのだろう。旅行の前後には教師から、太平洋戦争や沖縄の戦闘の概略について、説明を受けていることだろう。
学習の狙いをどこに置き、どの程度達成されたと教師たちが考えているのか、はわからない。ただ、いささか引っ掛かりを覚えたのは、これが「いのちの大切さを学ぶ」学習だとされることである。なぜ「歴史」の学習ではないのだろうか。それに、「いのちの大切さを学ぶ」学習、(あるいは「いのちの大切さを教える」教育)という言葉は、日本語として少しヘンなのではないか。
「いのちを粗末にするな」、「いのちを大切にしろ」という言葉の、意味するところは明瞭である。「いのち」も「粗末」も「大切」も、言葉を発した者と言葉を掛けられた者のあいだに共通の了解がある。行動の選択をめぐって激しくせめぎ合っていても、言葉自体の安定感に曖昧さはない。
しかし「いのちの大切さを学ぶ」、「いのちの大切さを教える」という言葉が口にされるとき、「いのち」も「大切さ」も抽象的な曖昧さのなかに揺らぎ始める。
それはあらためて学ばなければならないものなのか?それは学校教育で教えることができるものなのか?学習のあとに、心身にどういう変化が起これば、学んだことになるのか?学習の進度はどのように測られるのか?
また、沖縄の戦争で亡くなったのは、戦闘に巻き込まれた市民だけではない。負け戦を承知で戦った軍人や兵士たち、死を覚悟して赴任した「最後の沖縄県知事」島田叡(あきら)のような行政官もまた、沖縄の戦争に斃れたのだが、かれらの死は「いのちの大切さを学ぶ」ときに、どのように位置づけられるのか。
7.
島田叡については中野好夫が、『最後の沖縄県知事』(1961年 文芸春秋新社刊)という本を書いている。その中に引用されている池島信平の文章が、簡潔に島田叡を語っている。
《島田知事が沖縄に赴任したのは、もうだれの眼にも、次の戦場は沖縄と映じていた時である。こんな時になって、沖縄へ行くのは自殺しに行くようなものだといって、周囲の者はみな止めたが、「それでは、ほかの人間なら死んでもよいのか」といって、あえて死地に身を投じたのである。(中略) 三年前、沖縄へ行った時、私が耳にした限り、みな島田知事の死を心から惜しむ人ばかりであった。にくまれていい地位にある者が、これほどまでに慕われているということは、一体どうしたことであろうか。(中略) 沖縄ではだれ一人知らぬものとてない有名な人であるが、内地ではだれも知らない。私はそのことを悲しむ。》
島田知事はいのちを大切にしたのだろうか、それとも大切にしなかったのだろうか。せっかく沖縄まで生徒たちを連れて行くのだから、教師はそのような問いを生徒たちに投げかけてみてはどうだろうか。
もしも生徒のひとりが、「島田知事はいのちを大切にしたのだと思う」と答えたとするなら、その生徒のなかで「いのち」という言葉は生物学的生命の意味の枠から離れ、新たな意味の広がりを獲得しているといえるだろう。しかしそれは、「学習」を企画した教師たちの企図を超えたものであるはずだ。
子どもたちが歴史を学べば、その混迷、混乱、混沌から多くの問題を学びとることができる。
しかし、「いのちの大切さを学ぶ」という、大人も困惑するような問いの立て方から、子どもたちが何を学ぶことができるのか、筆者にはわからない。
8.
「新しい学力観」にもとづく「ゆとり教育」は、21世紀に入り、子どもの「学力低下」に対する社会からの囂囂たる非難の前に、事実上撤回を余儀なくされたようにみえる。
また、理論的な批判の試みとしては、刈谷剛彦による実証的で丁寧な検討が特筆される。
刈谷剛彦の研究によれば、「新しい学力観」、「ゆとり教育」、「生きる力」の教育、「子供中心主義」の教育など一連の教育改革は、誤った事実認識の上に構想されたものであり、教育現場での実現方法の検討も条件整備も不十分なまま進められたという。(『教育改革の幻想』 筑摩書房 2002年刊)
90年代を通じて子どもたちの学習時間は減少したが、なかでも元々学習時間の少なかった子どもたちの学習離れが進み、勉強をする子どもたちとの間の差が広がった。つまり、教育改革のなかで、改革の意図とは逆に教育格差は拡大し、学習意欲の格差も拡大している、と刈谷は指摘する。
大村はまが新制中学校の国語教師として活動を始めたのは、誰もが食べるだけで精いっぱいの時代であった。子どもたちは知識に飢え、むさぼるように吸収した。教師にとってやりがいのある、幸せな時代だった。
大村は現役教師を退職後、「大村はま国語教室の会」を主宰。2005年に百歳近い高齢で亡くなった。
*『新編 教えるということ』大村はま ちくま学芸文庫 1996年
ARCHIVESに戻る