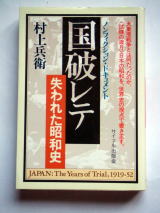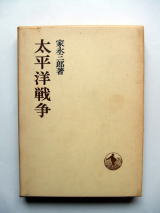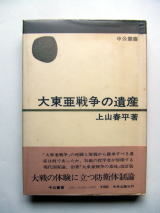『国破レテ――失われた昭和史――』
村上兵衛 (サイマル出版会1983年10月刊)
【ブログ掲載:2011年8月27日〜10月15日】
1.
この本の記述は1919年のベルサイユ会議に始まり、1952年のサンフランシスコ条約発効の時期で終わる。著者は謙遜して「ノンフィクション・ドキュメント」と呼ぶが、昭和前期の立派な通史である。
村上兵衛は大正12年の生れ、陸軍幼年学校から陸軍士官学校に進み、近衛歩兵連隊に勤務中に敗戦の日を迎えた。
戦後彼は、戦争についての書物、戦争の原因に関する書物をむさぼるように読み、考え続けた。しかし、いつまでたっても十全の答えは出なかった。歴史学者による「太平洋戦争史」や「昭和史」を読んでも、どこか白々しさや虚しさが残った。自分の体験した日本人の歴史とは、どこか食い違っているという思いを抑えることができなかった。
村上は小説を書き評論活動をする一方、財団法人・日本文化研究所で日本の文化、歴史、政治、経済について、広く海外に伝えるために英文書を制作・出版する仕事に従事した。しかし「あの戦争とあの時代」に触れない限り、海外の日本と日本人に対する理解は前進しない、ということを次第に痛感するようになった。
彼は自分が歴史学者ではなく、いわゆる歴史を書くことは不可能だと自覚していた。しかしあの時代を可能な限り忠実に再現する「ノンフィクション・ドキュメント」なら、自分にも書けるかもしれないと考え、それを「大胆に」試み、翻訳チームが英文に訳した。
昭和57年に出版されたその本は、好評を得た。「戦争は双方の丘から眺めるべきであって、その意味からこの本は非常に役立った」といったアメリカ人の一般読者からの批評が、著者を喜ばせた。その元原稿をもとに、彼は翌年、日本人読者に向けて新たに本書を書き下ろした。
《結果として、その内容においては、英語版とそれほど違わないものになった。しかし、つねに「世界」の読者を意識し、可能な限り公正な視野に立つ――という点では、右のような本書成立の経緯は有効にはたらいたのではないか》と著者は「ひそかな自負」を語っている。
2.
本書の特徴のひとつは、太平洋戦争の経過についての記述が「主体的」なことであろう。歴史学者の描く「昭和史」の多くが、戦争の経過をあたかも他動的な状況の変化のごとく扱うのに対し、村上は真珠湾やマレー半島にはじまり、ミッドウエー、ガダルカナル、レイテ沖、サイパン、硫黄島、沖縄へと進行した日米軍の戦闘を、具体的に記述する。
指揮官の判断の優劣の差が、劣勢な戦力しか持たないアメリカ海軍に圧倒的な勝利をもたらしたミッドウエーの海戦。兵站線の軽視、戦力の逐次投入、肉弾攻撃による夜襲を繰り返し、撤収するまでに戦死者8千人、飢えと下痢とマラリヤによる死者1万1千人を出したガナルカナル島の日本軍。
支援も補給も受けられず圧倒的な敵戦力と戦うことを強いられた硫黄島では、指揮官・栗林中将が伝統的な水際作戦を一擲し、岩山にこもってよく戦った。戦闘は1か月間続き、日本軍2万1千人が戦死し、アメリカ軍は2万3千人の死傷者を出して終わった。戦闘の初期、擂鉢山の山頂に星条旗を立てた写真で有名になった6人のアメリカ兵のうちの3人も戦死した……。
村上は戦争の全体の傾向を、次のように総括する。《アメリカ軍は、つねに前線からの報告を重視し、それによって戦略をフレキシブルに変え、現実に対応した。しかし日本軍は、陸軍士官学校と陸軍大学校の成績によって中央に陣取った“官僚"たちが采配を振るい、第一線で血と汗によって得た戦士たちのチエを、つねに無視しつづけた。》
3.
太平洋戦争の前史は、言うまでもなく日中戦争である。
日本は盧溝橋での日中両軍の衝突を、政治的にも軍事的にも収めることに失敗し、戦火は拡大し、日中間の戦争は泥沼に陥った。日本はこの行き詰った状況と不利に展開する国際関係を一挙に打開するために、太平洋戦争に突入した。村上は、盧溝橋事件発生後の日本側の動きと、指導者たちが戦闘終結を希望していたにもかかわらず戦火が拡大していった事情を、かなり丁寧に叙述している。
昭和12年7月7日の夜、北京郊外の盧溝橋で日中両軍が衝突した。
明治34年(1901年)のいわゆる北清事変で駐兵権を獲得していた日本軍の 一個中隊が、いつものように夜間演習を行っていたところ、中国軍からの射撃が頭上を通過した。《老練の清水節郎中隊長には、それが頭上高く通過する、イヤガラセの威嚇射撃であることはすぐわかった。》 しかし、ともかく演習を中止して点呼をとったところ、兵が1名欠けていた。それで大騒ぎになり、報告を受けた支那駐屯軍第一連隊長の牟田口廉也は大いに張り切り、増援部隊を現地に送った。行方不明の兵は20分後に発見されたが、日本側の謝罪要求と中国側の対応がもつれ、小競り合いが起こり、事態はしだいにエスカレートする気配を見せた。
駐屯軍の中にも、無益な事態の拡大を阻止すべきだと確信し、両軍の間の交渉を苦労して進めたスタッフがおり、現地における停戦協定にこぎつけた。
しかしその協定がやっと調印された前日、陸軍中央は内地から三個師団、朝鮮から一個師団、満州から二個旅団の動員を決定していた。
当時、この事件の処理を巡り、陸軍の意見は真二つに割れていた。陸軍省は、中国軍に本格的な一撃を加えるならば相手は譲歩する、という主戦論が支配していた。杉山陸軍大臣は事態を懸念する天皇に、支那における戦争は一か月もすれば片付くと存じます、と奏上している。
一方参謀本部は、大陸で事を起こすのは不得策と考え、動員計画に強く反対した。その反対の中心は石原莞爾第一部長だったが、《慢性的な胃病と不眠不休の勤務――そのときの彼は、参謀本部の重要な仕事の一切を、ひっかぶっている観があった――による疲労困憊の中で、うかうか動員計画にサインした。》
盧溝橋事件のひと月前に総理大臣の地位についた近衛文麿は、はじめのうちは動員計画に消極的だったが、勇ましい主戦派の意見を聞くとそちらに動かされ、計画に同意した。
派兵決定の知らせは現地駐屯軍における主戦派を力づけ、不拡大派の影響力を低下させた。そして蒋介石に重大な決意を強いることになった。
それまで蒋は、日本と戦うことを可能な限り避け、日本との協調の道を探り、まず中国の統一と改革を行うことを方針としてきた。その蒋介石が中国国民に向かって次のように訴えた。
《「満州が喪われてすでに六年、日本との衝突の場は、今や北平(北京)に近づいた。北平が第二の奉天になるならば、首都南京もまた、同じ運命をたどるであろう。盧溝橋における事件の解決には、まさに中国の命運がかかっている。(中略)
わが国は、もとより弱国である。しかし、我々は我々の民族の生命を保持し、祖先から伝えられた歴史にたいして責任を担わなければならない」
その訴えは中国の第一線の兵士たちを鼓舞した。日本軍との間には頻繁な衝突が起こり、日本軍は全面的な攻撃を開始した。》
日本軍は北京・天津を占領し、中国北部において連戦連勝の快進撃をつづけ、新聞は連日、その戦況をはなばなしく報道した。
《国民は「暴支膺懲」のキャッチフレーズと疾風枯葉を巻く皇軍の快進撃に沸き、この戦争の本質を考えることを忘れた。すなわち、今度の事変は中国にとっては国家の存亡をかけた、止むを得ざる必死の抵抗であり、いっぽう日本にとっては、ほとんど名分の立たない“汚い戦争“である事実を……。》
近衛は状況に苦慮しながら、考えは微妙に揺れ動いた。彼が望んだのは、あくまでも武力の顕示による中国側の譲歩であり、事件を短期に解決することであったが、事態は思惑を外れ、全面的な戦争に発展する気配があった。
近衛は石原から「首相みずから南京に赴き蒋介石と会談を行わないかぎり、事態収拾の道はない」という進言を受け、一時は真剣にそのことも考えた。しかし結局、動かなかった。
《その逡巡の最大の理由は、もし両首脳のあいだで交渉がまとまっても、それが現地の日本軍の勝手な行動によって破られたならば、かえって国際信用にかかわる――というにあった。
彼は、今度の衝突を仕組んだのは、満州事変のときと同様、わが陸軍ではないか、と疑い、ほとんどそう信じていた。》
昭和13年1月、盧溝橋事件から半年を経過し、近衛首相はドイツの駐華大使トラウトマンを通じての蒋介石との交渉を打ち切り、「国民政府を相手にせず、日本と提携する新政権の成立を期待し、これと国交を調整し、新しい支那の建設に協力する」と声明を発表した。―――
よく知られている盧溝橋事件の発端とその後の戦火拡大の経緯を、村上の叙述に従って長々と記述したのは、関係するひとびとの思いや苦闘、迷いや驕り、判断の誤りや偶然の成り行きが、事態を誰もが望まぬ方向に押し流していく様子を、あらためて確認したかったからである。村上は歴史の皮肉な展開を、流れを見失うことなく、また高みから裁断するのでもなく、ていねいにバランスよく描いていると思う。
おそらく歴史書の読者がもっとも「歴史」を感じるのは、そういう歴史の現場の混乱や混迷、混沌に接したときであろう。
他方、後世の超越的基準で裁断、整理された記述を読まされるとき、その主張への賛否は別として、それが「歴史」の叙述であるとは認めがたいのではなかろうか。
4.
家永三郎『太平洋戦争』(1968年2月 岩波書店刊)という書物がある。
著者は昭和史の専門家ではないが、「日本近代史の研究者の一人として、太平洋戦争の歴史的理解を回避すること」は許されない、という思いから、「僅々数年の準備」ののちに「熱情をこめて執筆に当たった」。「著者の専門的能力の及ばない、戦争の経済的基盤の考察とか、支配者層内部の動き、外交折衝、戦闘の経過等についての細部にわたる追跡とか、外国の側での戦争への対処の仕方の精考とかは、初めから断念」して問題をしぼり、「この戦争の歴史的本質」、「この戦争の一番大切な点の理解には欠けることのないよう配慮」したという。
この書の前半四分の一ほどが、「戦争はどうして阻止できなかったのか」という家永の設定した問いと回答の部分であり(第一篇)、残りの四分の三が「戦争はどのようにして進められ、どのような結果をもたらしたか」と題された、張作霖爆殺以降、太平洋戦争終結までの歴史記述になっている。(第二編)。
戦争はどうして阻止できなかったのか。家永の答えは次のようである。
国民の間に中国、朝鮮への誤った優越意識があり、戦争に対する批判的な意見は治安立法により抑圧され、また教育によって軍国主義の方向へ国民の意識が画一化されたこと、そして日本の「軍の反民主性、非合理性」が原因で、日本は戦争に突き進んだ、という。
「軍の反民主性、非合理性」とはよくわからない言葉だが、統帥権が天皇に帰属するという憲法上の規定を乱用し、軍が国政を望む方向に引っ張っていったことなどを指す、と理解しておこう。
そのような「まえおき」を置いて記述した第二編の歴史叙述だが、読後感を先に言えば、無味乾燥で平板、つまらないの一語に尽きる。その「つまらなさ」の原因を探ると、ひとつの理由は、家永が「専門的能力が及ばない」と「初めから断念」したことがらに関わってくる。
政治・軍事指導者の判断や行動、相手側の事情や外交折衝を、家永は「初めから断念」したというが、それを記述せずに戦争の歴史を描けるのか、という疑問がまず起こる。戦闘がどのように行われ、その勝敗の原因がどこにあったのかに触れずに、なぜ戦争の歴史を語れるのか。家永の、注や「あとがき」まで入れれば350ページ近くなる書物のうち、太平洋戦争の戦闘の記述に割かれたのは、実質わずか5ページにすぎない。
家永の「ことわり」の言葉は一見謙虚な姿勢のように見えながら、実は歴史家としてかなり傲慢な態度だったのではないか。
しかし「つまらなさ」のより大きな原因は、家永が「この戦争の歴史的本質」、「この戦争の一番大事な点」と呼んで力を入れた点、その叙述の姿勢に関わるように思われる。
《満州事変は、確かにその企画に照らして考えるならば、大成功であったといわねばならない。しかしこの大成功に酔った侵略主義者たちはそれだけで満足せず、あくことを知らぬ侵略欲を充足するために、満州から蒙古・華北へと軍事的支配地域を拡大して行くことにより、自ら墓穴を掘る愚を演じた(以下略)。》
《「支那事変」の開始に関しては、陸軍中央部にも、また出先にも拡大派と不拡大派との対立があり、不拡大派に属する人々は、責任をあげて拡大派の側に転嫁しようとしているけれど、大局的客観的にみるときには、両者の対立は畢竟コップの中の嵐にすぎず、本質的な戦争観の対立であったと考えるのはむつかしい。》
《(前略)不拡大派でも中国侵略の全面放棄を考えていたのではない。彼らの究極目標はソ連との戦争に施行されていたのであり、そのために対ソ前線基地としての「満州国」の育成に専念せよというのがその真意であった。しかしもともと不法に中国から侵奪した満州を掌握したまま中国との平和友好関係を回復しようというのであるから、不拡大派がどのような性質のものであったかは、これだけでおのずからうかがわれるであろう。》
家永は、後世に生きる者の特権の上に立ち、日本の過去の行状を述べながら、批判し断罪することに精力を注ぐ。侵略主義者、軍国主義者が国内の批判を抑圧し、中国侵略から対米戦争に国民を引きずり込んでいった歴史として、昭和史をとらえる。(彼が「この戦争の歴史的本質」と呼んだのは、おそらくそのことだ。)
作業上の仮説をもって過去の資料に取り組むのは、別におかしなことではない。しかし単純化された図式に従って、資料から都合の良い部分を引き出し、貼り付け、それにとどまるような作業が、歴史を語ることだとはひとは言わないだろう。
家永は過去の出来事を素材に自分の思いを熱く語りはするが、歴史を語ってはいない。彼の叙述が無味乾燥で平板になるのは、このためだ。それは「歴史評論」ではあっても歴史書とは呼びがたい。
安全な場所からの一方的な断罪ではなく、当時の人々の思いや判断の誤り、人間的な弱さや驕り、苦しみや喜びにていねいに耳を傾けるなら、もっと厚みのあるバランスのとれた歴史叙述が可能になっただろう、と思う。
「支那事変」の始まりを村上兵衛がどのように描いたかを、前節に小さく示した。十五年戦争の歴史を記述した村上の優れた書物は「ノンフィクション・ドキュメント」として出版され、「歴史」を素材に自分の「思い」を述べたに過ぎない家永三郎の「評論」が「日本歴史叢書」の1冊として刊行されたのは、皮肉というべきだろうか。
5.
日本軍のアジア各地への進攻と、それがアジアの民衆に与えた影響について取り上げたい。
日本の戦争の評価をめぐって主張が対立するポイントの最大のものが、この戦争の目的と戦後のアジア諸国の独立との関係であるからだ。
また、前節で筆者は、「家永は歴史を語っていない。自分の図式に合う資料を拾い集め、貼り付けているだけだ」という趣旨の、いささか性急な断定を下したが、具体的に彼の記述を点検することで、断定を補足したいと思う。
1941年12月8日未明、日本軍はハワイ島真珠湾の攻撃を行うと同時に、マレー半島に上陸を開始した。
以下、年表風に記せば、12月10日:マレー沖海戦 英海軍の戦艦「プリンス・オブ・ウエールズ」、「レパルス」を撃沈。同日、フィリッピン北部に上陸。12月12日:閣議で戦争の名称を支那事変も含めて「大東亜戦争」とすることに決定。1942年1月2日:マニラを占領。2月15日:シンガポールの英軍降伏。3月1日:日本軍、ジャワ島へ上陸。3月8日;ラングーンを占領。3月9日:ジャワのオランダ軍降伏。5月7日:マニラ湾のコレヒドール島に立てこもった米軍降伏。―――と開戦後半年間は、日本の順調な連戦連勝が続いた。
村上兵衛は次のように述べる。
《シンガポールの陥落は、ひとつの歴史的な事件であった。十六世紀以来、東洋に進出し、東洋に君臨していたイギリスの最大の根拠地が消え、かわってアジアの一国の日本が、支配者の地位についた。
その事実は、ほとんど全アジア人――中国人とフィリッピンの指導階級の一部を除いて――から、満足の念を持って眺められた。》
《マレーおよびシンガポールで、もっとも頑強に抵抗したのは、華僑から成る義勇兵であった。彼らにとって日本軍の進攻は侵略であって解放ではなかった。祖国である“中国”と、ともに戦う意思を示した彼らは、得意のゲリラ戦によって日本の進撃を悩ました。(中略)シンガポール島の攻防が行われたときは、雪崩を打って退却する英印軍と対照的に、彼らはさいごまでたたかった。要塞の北西部を守備地域に割りあてられた中国人義勇隊はさいごの一兵まで、そこで銃を握ったまま戦死した。》
《マレー人はまず日本軍による解放を歓迎し、協力した。
ひとり中国人は強烈な敵意を失うことなく、ゲリラ戦をつづけようと試みた。
日本軍は、押収した抗日華僑名簿によって六千五百人を逮捕し、裁判にかけることなく、そのうちの五千名を処刑した。これは、この大戦中、日本軍によって行われた最大規模の粛清だった。》
《米英との開戦にあたって、日本政府は自衛のためとうたい、さらにアジアの解放を訴えた。それは、ある意味においては正しかった。(中略)
しかし、日本が中国に対してとっている現実の態度に照らすならば、日本が“聖なる使命”を担っている、と主張するのは僭越だった。》
占領に続く軍政については触れられていないが、よくバランスのとれた、妥当な記述といえる。
他方、家永三郎はどのように語るか。彼の『太平洋戦争』は「『大東亜共栄圏』の実態」という1章を立て、地域別に、多数の手記を引用して日本軍の進攻の「実態」を述べる。
マレーについては、次のように述べる。
《華僑が人口の多数を占めるシンガポールでは、抗日意識が強く、中国への献金ばかりでなく、日本軍への後方攪乱などまで行った。日本軍はシンガポール占領後、抗日華僑7万余を検挙し、数千人を処刑した。「しかも、その処刑のやり方も、例えば多数のものを数珠つなぎにして船で沖合に運び、そのまま突き落としてしまうという残虐な手段がとられ」たともいう。(中略)
抗日や犯罪に対する惨刑だけでなく、一般住民への暴行も相当行われたらしい。強姦のあとでひそかに拳銃を上衣の下にかくし、女が「隙をうかがって逃げ出したりするのを、すぐ拳銃を後からぶっぱなしたり」した例も伝えられている。中国戦線よりも「軍紀は概して良好で」あったというけれど、右のような事例のほか、「女の死体の陰部などに竹の棒をさし込むような凌辱を加えられてあったのを一度だけ見た」という記録もある。
シンガポールの住民にとっては、「口やかましく尊大な英人の代わりに、乱暴で下品な日本人の支配者になったというだけのことであった。(以下略)」》
インドについては、わずかに10行だが、次のようなことが書かれている。
《四二年九月、日本軍はインド国民軍を編成した。しかし、インド人側が国民軍の独立性・自主性を主張するのに対して、日本側は日本軍に対する作戦協力をあくまで主張し、国民軍との間に感情の疎隔が大きくなった。(中略)
チャンドラ・ボースのように、日本の力をかりてインドの独立をはかろうとしたものもいたが、多くのインド人は英軍とともに進んで日本軍とたたかった。これより先、日本軍が中国全土に進撃を行っていたころ、インド国民会議派のネルーは中国医療委員会を組織し、また「中国デー」を作り、中国支援のために日貨ボイコットを民衆に呼びかけた。》
インドネシアについては、次のように書く。
《インドネシア人もまた、ビルマ人と同様、はじめ日本を歓迎し、まもなく失望に変っていった。(中略)
他の支配地でと同様に、「街を歩く日本人は、現地人を見下し、酔っぱらっては人のいいペチャ(三輪車)をなぐりつけ」、「料理屋の青畳の上では将校が女にたわむれ、カフェーのボックスでは下級将校や軍属たちが、あいかわらず放歌高吟をくりかえしている」光景がみられた。》
《「人の頭は非常に尊いものとされ、頭に触れる事すら」タブーとする「慣習を持っている住民の頭を、日本軍は街の真中でさしたる理由もなく殴りつけた」。「住民の悉くが日本人を怖れていた。人々は昼日なか街さえ自由には歩けなかった」。ヘラワティ・ディアの妹サプリタは日本人に強姦され、発狂して廃人となった。
敗戦後アンボンで戦犯の処刑が行われたとき、「見物に集まってきた者たちは、みな一様に、日本人に対する憎悪と冷笑の目で見守」り、「われわれの食物を奪ったニッポンをやっつけろ」「ざまみろ、早く死んじまえ」と「火のような憎しみ」の叫びをあげたという一例をみても、民衆がどれほど深く日本の圧政を憎悪していたかが窺われるであろう。》
要するに家永の書いた本では、日本の占領、軍政が民衆から憎悪されていたことが強調され、その原因として日本兵の強姦や殺戮、虐待、拷問、略奪、暴行の話が、記録や手記から抽出されテンコ盛りになっている。
《日本の力によってアジア諸民族が独立したのではなく、アジア諸民族は日本に抵抗することによって独立を達成したのである。日本にとって恥辱でこそあれ、それを日本の功績として誇るがごときは、およそ真実に反した逆立ちの評価とされねばならないであろう。》と家永は結論する。
少々おとなげない気もするが、家永のデタラメな発言を指摘するところから、問題を解きほぐそう。
日本軍が占領した地域では、それまで支配していたイギリス、オランダ、フランスの力は排除された。しかし日本が降伏したあと、旧勢力は支配権を再び握るために軍隊を送りこみ、現地の日本軍から武器の引き渡しを受け、施政権を奪還した。その後アジア諸民族は、ヨーロッパの植民地主義者と戦うことによって独立を達成したのである。
「アジア諸民族は日本に抵抗することによって独立を達成した」という家永の記述は、だからデタラメである。ただ、なぜ家永が誰の目にも明白な誤りを犯したのかを、想像することはできるように思う。アジア諸国の独立に与えた日本占領の影響を無視したい、という意識下の強い思いが働き、つい”筆が滑った”のではないか。彼は、日本の蛮行に対する抵抗が、諸民族の目覚めを生み、それが独立を達成させる原動力になった、と言いたかったのではなかろうか。
しかしアジア諸民族の“目覚め”にとって、旧支配者が一時的とはいえ一掃された経験は、なによりも大きかったはずである。また、自分たちの支配者が一掃されたわけではなくとも、アジアの各地で植民地帝国の軍隊が打ち破られ、日本軍に占領されたというニュースは、大きな衝撃をもってアジア諸民族の“目覚め”を促したにちがいない。
日本の指導者は「アジアの解放」をスローガンとして掲げたが、それをアジアの諸民族のために望んでいたわけではない。にもかかわらず、日本がアジア各地を占領したことにより諸民族が目覚め、一度目覚めた諸民族の思いは奔流となり、彼らは独立した。そういう歴史の皮肉な事実を、家永は躍起になって否定しようとするが、歴史の皮肉を認めずに歴史を語れるはずがない。
6.
日本軍のアジア各地への進攻と、それがアジアの民衆に与えた影響について、いましばらく話を続けたい。まず、インドについて。
四十二年四月、日本海軍はインド洋に進出し、コロンボなどを空爆したが、イギリスのインド支配に対して直接的な打撃は与えていない。しかし大戦の影響は、確実にインドの民衆に及んだと見るべきである。村上の叙述を見てみよう。
《開戦に先立ち、陸軍の藤原岩市少佐は、バンコックにおいて秘密機関インド独立連盟(IIL)のメンバーと接触し、彼らは日本軍とともにマレー半島を南下した。》
《一九四二年(昭一七)二月十五日、英軍は白旗を掲げ、シンガポールは陥落した。
その二日後、藤原少佐はインド兵捕虜を、ファラ・パークにおいて接収した。公園は、昼ごろから雲霞のように集まってくるインド将兵によって埋め尽くされ(中略)た。
藤原少佐は、今度の戦争の意義とインド独立について演説し、IILとモハン・シン大尉の率いるINA(インド国民軍)の活躍について紹介した。
そして、彼が、「インド兵諸君が自ら進んで祖国の解放と独立の戦に参加するならば、日本軍は諸君の捕虜としての取り扱いを停止し、闘争の自由を認め、全面的支援を与える」と述べると、インド兵は総立ちになり、歓呼のどよめきとともに帽子が空に投げ上げられた。
インド国民軍に編成された彼ら二万の主力は、祖国解放を目指してビルマに向かうことになった。
この噂はたちまちインドにも伝わり、ネールは「インド人も人種・階級の差異にもかかわらず協力する能力のある事実」に、深い感銘を受けた。》
読者は村上の叙述から、歴史の胎動を聞くことができる。しかし家永の「強姦、殺戮テンコ盛り」の叙述から、歴史の流れを読み取ることは困難であろう。
「民衆が深く日本の圧政を憎悪していた」と家永が書くインドネシアの事情について、最後に考えてみたい。
日本軍が占領した各地の軍政は、戦争遂行の必要から多くの現地人を労務者として徴用し、荷役や軍用道路の建設、陣地構築、軍需工場などの労働に使役した。またタイとビルマを結ぶ泰緬鉄道の建設(『戦場にかける橋』!)のために6万2千人の連合軍捕虜とその数倍の東南アジアの人々を集め、突貫工事を行った。
占領地には徴用令は適用されていなかったから、ロームシャは自発的に応募したという形をとった。しかし実際は騙されたり、有無を言わせず連行されたケースが多かったという。(『「大東亜戦争」を知っていますか』倉沢愛子 2002年6月刊)
ロームシャの待遇も労働環境も最低だった。「ロームシャ」はインドネシアにおいて、日本の圧政への怨嗟を象徴する言葉となった。
一方、連合軍の反攻が本格化した1943年10月、「ジャワ防衛義勇軍」の創設が日本軍の最高指揮官名で布告された。若者に参加を呼びかけるポスターが街角に貼りだされ、義勇軍の幹部を採用する試験が各州の首都で行われると、どこでも試験場にあふれるほどの青年たちが詰めかけた。そうして採用されたインドネシアの青年たちを集め、日本軍から派遣された指導者が日本の陸軍士官学校に準じた教育を行った。短期間であるが厳しい錬成教育の下、幹部候補生たちはたちまち見違えるほど逞しくなった。彼らを幹部とする防衛義勇軍が、各地に配置された。
義勇軍は日本の敗戦とともに、日本軍の命令で解散した。しかし進駐してきたイギリス軍、オランダ軍に対し、インドネシア人は防衛義勇軍を再建して戦い、1949年に独立を達成した。日本軍兵士は敗戦とともに連合軍の捕虜となり武装解除されたが、約700人の兵士は各地で義勇軍とともに戦う道を選び、約400人が戦死した。
村上兵衛は80年代の初め、中国、ビルマ、インドネシアなどを歩き、また戦時中、「南方特別留学生」として日本に留学したかっての若者たちに会い、それをルポルタージュにまとめている。(『アジアに播かれた種子』村上兵衛 昭和63年2月刊)
上に述べたインドネシアの「防衛義勇軍」創設の歴史は、村上の著書から摘記したものだが、彼は、かって日本人指導者の錬成教育を受け、「防衛義勇軍」の青年幹部として独立戦争を戦った男の言葉を記している。
「あるオランダの小説家が、インドネシアは日本から独立を買った、と書いているのを読んだことがありますが、これはまったく違います。われわれは日本から教育を得たのです。その教育によってわれわれは自信を得、自分たちの力でたたかい、そして独立を獲得したのです。」
7.
この連載の2回目、『国破レテ』2をアップロードした9月9日の新聞夕刊に、遠山茂樹の訃報が出ていた。8月31日逝去、享年97歳。説明に、《1951年に出版した「明治維新」で注目された。55年に共著「昭和史」(岩波新書)がベストセラーとなり、歴史の描き方をめぐって論争も呼んだ。》とあった。
亀井勝一郎が、遠山茂樹・今井清一・藤原彰共著の『昭和史』を批判する「現代歴史家への疑問」という文章を発表し、論争の口火を切ったのは、発行の翌年、1956年(「文芸春秋」3月号)である。
亀井は、歴史家はまず文学者に劣らぬ文章家でなければならない、と主張し、《これは第一の要求として掲げて少しも無理でないと思ふ。何故なら歴史とは、「人間を描く」行為だからだ。人間を描くことにおいて魅力を創造しなければならないし、魅力とは説得力のことである。》と言った。
また、歴史家は追体験の上に立って叙述すべきだとも主張した。《あらゆる時代の人間は、是非善悪はあるが、その時代を彼なりに精一杯に生きそして死ぬ。その運命を直視せよと言ひたい。もし自分がその時代その環境に生きたなら、自分はどうであったかといふ「追体験」の上に立って判断すべきではないか。》
そういう歴史家に求められる資格を念頭に置いて『昭和史』を見ると、《現代歴史家の欠点を、これほど露出してゐる本もない》と亀井は断定する。彼は致命的な欠点を、4点挙げた。
第1に、ここに描かれたのは「国民」不在の歴史である。《敗戦に導いた元凶とか、階級闘争の戦士の名は出てくる。ところがかうした歴史に必ずあらはれねばならない筈の「国民」が不在だ。これはどういふうことだらうか。日華事変から太平洋戦争にいたるまで、無謀の戦ひであったにせよ、それを支持した「国民」がゐた筈である。昭和の三十年間を通じて、その国民の表情や感情がどんな風に変化したのか。この大切な主題を、どうして無視してしまったのか。》
第2に、人物の描写が貧弱な点。
第3に、昭和史が戦争の歴史であったにもかかわらず、《死者の声が全然ひびいていない》こと。《歴史家とは死者の声を代弁し、その魂をよみがへらせるものでなければならない。死者の声に鈍感な歴史家などある筈はないが、どうしてそれを無視したのか。》
第4に、ソ連が中立条約を破り満州に侵攻し、多くの悲劇が生まれた事実に関し、ソ連に甘く日本に辛い公正でない記述。
遠山茂樹は反論を、同年の「中央公論」6月号に発表した。(「現代史研究の問題点 ―-―『昭和史』の批判に関連して――」)内容はドグマティックで亀井の批判とすれ違う部分も多いが、遠山が自分たちの考える歴史叙述について率直に語ったことは、いちおう評価してよいだろう。
遠山は次のように言う。
《文学は、人間およびその生活が、いかに個性的なもの、偶然的なもの、かけがえのない特殊において存在するかを描く……。ところが歴史学はそうではない。個性の差をふくみこみながら、人間が階級として存在すること、偶然を貫きながら必然性が実現されてゆくことこそ、あきらかにするのである。》
《歴史を変革するものの立場に歴史家の眼をすえて、歴史の動きをとらえるからこそ、その歴史批判は、内在的であり、しかも客観性を持つことができる。現存秩序を維持しようとするものの立場に立って、どうしてその秩序の全面的把握が可能であるのだろうか。戦争とファッショ的支配の正体は、それから一片の利益も得ぬはずの階級だけが、これを自由に徹底的に追及することができる。》
《歴史の真実と国民の感覚との間の、大きなずれは、至急正しい方法でうめられなければならない。それが果たされなければ、現代史の科学的認識は、国民の武器となることはできない。「国民感情」といわれる、おくれた意識にうったえて、かっての軍国主義への郷愁をかきたてようとする企てを、うちやぶることはできない。》
唐突なようだが、ここではこれ以上、遠山茂樹の歴史叙述の問題には踏み込まない。じつは亀井勝一郎の「現代歴史家への疑問」の中に、家永三郎について触れた部分があり、それがこれまで論じてきた点とも関わりがあるので、それを紹介するのが今回の目的である。以下、寄り道は切り上げ、本論に戻る。
亀井が歴史家の資質として、「追体験」できる能力をあげたことは、先に述べた。亀井は、歴史家がしばしば使う「限界」という言葉を自分は好まない、といい、人物の「限界」を言い立てることは正当だろうかと、疑問を投げる。《史上の人物の欠陥に目を閉じよといふのではない。矛盾を自己の矛盾として、彼とひとしい体験を担えといひたい。》
その亀井が例に挙げるのが、家永三郎の著作である。彼は家永の『近代精神とその限界』や『日本近代思想史研究』を読んで、いつもそこに「ひっかゝる」と言い、次のように続ける。
《(家永は)「反近代主義の歴史的考察」という論文で、田岡嶺雲や内村鑑三について考察しているが、彼らの近代悪への鋭い批判を賞揚し、同時に、その復古性に「限界」をみている。そう断定するときの家永氏の心理状態に私は興味をもつのだ。》
《現代人である私たちから見れば、過去の人物で「限界」のないものはひとりもいないことになるのだが、さういふものの感じ方や断定ぶりが私には納得出来ないのだ。それなら私たち自身の「限界」は一体どうなるのか。それとも「限界」などないのか。まさかさうではあるまい。つまり不用意にかういう言葉を使ふ人間の傲慢さが私の気にいらないのである。》
亀井が「ひっかゝる」と言い、「納得できない」と言い、「気にいらない」と言う点は、歴史叙述の基本的姿勢に関わることである。それは筆者が家永の『太平洋戦争』の叙述について、「後世に生きる者の特権の上に立」った批判、「安全な場所からの一方的な断罪」と批判したこととも密接に繋がっている。要するに亀井や筆者の見立てでは、家永三郎は歴史を叙述する姿勢において大きな欠陥をもつと言わざるをえない。―――
この連載は、村上兵衛の『国破レテ』を紹介し、それが優れた歴史書であることを示すために家永の『太平洋戦争』との比較を始め、『太平洋戦争』が歴史書として平板でつまらない理由を探るうちに、話は歴史家としての家永三郎批判に進んでしまった。しかし筆者は家永について、痩せた体躯に似合わず精力的に著述を行う奇矯な人物だった、という印象を持つだけで、特別な関心があるわけではない。また、力を入れて批判する価値のある対象とも考えていない。
次回に「太平洋戦争」あるいは「大東亜戦争」の意味について少し考え、連載を閉じることとしたい。
8.
「大東亜戦争」という呼称は、対英米戦を開始した昭和16年12月12日に閣議決定され、敗戦後の昭和20年12月15日、国家神道・神社神道についての連合軍司令部覚書により、使用を禁止された。GHQはその代わりに「太平洋戦争」という呼称の使用を命じ、「朝日」、「毎日」、「読売」などの全国紙に「太平洋戦争史」というGHQ作成の記事を、いっせいに連載させた。つまり、戦争に対するアメリカ側の解釈を示した。
《占領軍の示した「太平洋戦争」史観によれば、民主主義的な連合諸国(米・英・ソ・仏など)は平和愛好的で、ファシズム的な枢軸諸国(日・独・伊など)は好戦的であり、第二次大戦は枢軸諸国の一方的犯罪行為である》という主張になる、しかしそれは錯誤ではないかと上山春平は論じた。(『大東亜戦争の遺産』昭和47年 中央公論社)
上山は大正10年生まれ、京都大学の哲学科を卒業した研究者であったが、徴兵により「人間魚雷・回天」の搭乗員となった。彼はのちに当時の自分を振り返り、ヨーロッパからの植民地解放や東亜共栄という理想を、戦友たちと共有していたことを確認する。その思いを彼は、戦後もしばらくは執拗に懐きつづけた。
しかし日本の植民地支配の実態を知らされ、また軍人や時局便乗者の狭量な自国本位の考えによって、自分たちの理想が踏みにじられた現実を知らされる。日本がヨーロッパ植民地帝国から奪いとった東亜の支配権を、仮に持ち続けたとすれば、植民地の独立は本当に行われたのか、それは朝鮮や満州の統治政策の実態からみて、はなはだ疑わしい。
そう考える上山が「大東亜戦争」という言葉をあえて用いて議論を展開したのは、その言葉がタブー視され、それをタブーとみなす心理のうちに、「太平洋戦争」史観が特定の国家利益と結びついたひとつの史観であることを見ようとしない錯誤を認めたからである。
《戦後、「大東亜戦争」史観と国家利益の関係については克明な批判が展開されたにもかかわらず、それらの批判の立脚点とされた「太平洋戦争」史観や「帝国主義戦争」史観などはしばしば額面どおり普遍的な人類的尺度として受け入れられ、それらと特定の国家利益との暗黙の結合については批判的な省察の加えられる機会が少なかった。》
《私たちは、戦後、「大東亜戦争」史観の虚偽にめざめる機会をもちながら、残念なことに、「太平洋戦争」史観や「帝国主義戦争」史観の虚偽を新たに受け入れてしまった。》
だが上山がそう主張する根拠は、それぞれの「史観」の問題点を比較考察したからではない。原理的に、主権国家は戦争をする権限を持つ存在であり、戦争行為のゆえに他の主権国家から裁かれるというのはナンセンス、と考えるからである。上山の議論はここから、主権国家を超えた高次の国際組織の必要性の問題に進むのだが、ここでは省略する。
ただ次のことは、指摘しておかなければならないだろう。国家によって主張される「史観」が、いずれも特定の国家利益と結びついているのはそのとおりとして、そのイデオロギー的説得力には差異があり、統治・支配の巧拙とも絡んで、「太平洋戦争」史観は現実に大きな普及力をもったことである。その要因として、検閲や宣伝の巧みさや史観(イデオロギー)操作の面だけを強調することは、平衡を欠く。「太平洋戦争」史観を受容させる客観的条件が日本国民の側にあったのであり、それがアメリカ占領軍の「最も成功した占領統治」を可能にした。歴史を考える場合、上山のように原理的な思考だけで済ますわけにはいかない。
上山春平が、前掲の『大東亜戦争の遺産』所収の論文「大東亜戦争の思想史的意義」を発表した翌年、林房雄が『大東亜戦争肯定論』を雑誌に連載した。(「中央公論」1962年)。
林房雄はそこで、「大東亜戦争は形は侵略戦争に見えたが、本質においては解放戦争であった。」「日本は敗北し玉砕したかのように見えたが、目的は達成された」と主張したのだが、上山は「あの戦争は侵略戦争であり、その目的は完全な失敗に終わったと見るべきだ」と述べる。
上山は昭和15年6月に陸軍省を中心に立案された「総合国策十年計画」や、翌7月に閣議決定された「基本国策要綱」などを検討し、欧米との対決意識は旺盛だが植民地解放の思想は希薄であることを指摘する。そして、「私は、植民地解放戦争とみるよりはむしろ植民地再編成をめざす戦争とみる方が事実に即しているように思う」と書いた。
《要するに、林氏は、戦後のアジアにおける民族解放の事実を大東亜戦争の目的の達成とみているのであるが、私は、逆に、目的の挫折の結果とみるのである。白人によるアジア人の支配は植民地化であるが、アジア人の支配は植民地解放である、とでもいった考えを前提にせぬかぎり、明治以降の日本の膨張過程を植民地解放の過程とみなすことは困難であり、その侵略行為を解放戦争とみることは不可能である。》
この上山の言葉に、これ以上加えることはない。村上兵衛の『国破レテ』に今次大戦の意味について明示的に論じた部分はないが、上山の上の発言に異議はないのではないかと思われる。
(終)
ARCHIVESに戻る