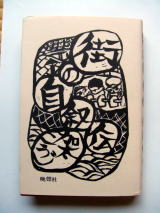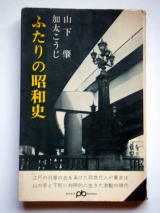『街の自叙伝』 『ふたりの昭和史』
加太こうじ
【ブログ掲載:2011年7月11日】
1.
滝田ゆうの漫画『寺島町奇譚』に「ぬけられます」という不思議な看板が出てくる。
舞台は戦時下の向島区寺島町。少年の眼から見た庶民の暮らしと街の様子が、哀愁を込めて妙にリアルに描かれている。
場末の街のごみごみした路地の上に、右から左に大きく「ぬけられます」と横書きされた看板がかかっている。縦書きされ電柱に付けられた袖看板もある。他にも「ちかみち」「安全道路」といった看板も出てくるから、一杯呑み屋や玉ノ井の私娼窟が客を呼び込むために取りつけたものだろうと、漫画を見ながら漠然と推測した。
その理解が正しいのかどうか、確認したことはない。が、おそらく間違いではないだろうと得心がいったのは、もっと後になって加太こうじの文章を読んだ時である。
《尾久の道には行き止まりがない。どんな細い道でも――人ひとりが、やっと通れるような路地でも――家と家の間を通りぬけて大通りへ出られた。それは、どの家も塀や垣根がなく、ひしめきあうように建っていたからである。》(『街の自叙伝』)
尾久は荒川区であり、寺島町のある向島区とは隅田川を挟んで反対側に位置するわけだし、滝田ゆうの描く街には板塀のある家も見える。しかし基本的には尾久の街も寺島町も、貧しい家々がひしめくように軒を接し、路地は行き止まりにならずどこかに抜けられるという点で、変わるところはなかった。「ぬけられます」は客の呼び込み文句であるとともに、正しい道路情報の提供だった。
2.
加太こうじは大正7年に生れ、尾久で育った。尾久は関東大震災のあと、下町を焼け出された職人や小商人が移り住み、安普請の長屋が立ち並ぶ市街地となった。加太が高等小学校に通う頃は、「迷路のような路地と、異様な悪臭を放つ溝と、二三日雨が降りつづくと、大通りから横丁まで、高下駄デモもぐってしまうような、ぬかるみの町」だった。
絵の上手だった加太は、昭和6年、高等小学校2年の時から生活のために、紙芝居づくりのアルバイトを始める。翌年、逓信省の給仕の試験に合格するが、とても一家5人を養う収入を得られないと一日で見切りをつけ、紙芝居の製作に専念することにした。
加太の仕事は順調に進み、ヒット作を出すたびに収入は増え、二十歳にならぬ身で月収120円を稼ぎ出した。これは当時の小学校の校長よりも多かった。
日本は年ごとに戦時色を強め、友人たちも次々に徴兵された。しかし加太は、小学生のとき剣道で鼓膜を破られ右耳が全然聞こえないため、徴兵検査は丙種合格となり、徴兵は免れた。
紙芝居の貸元が統合され、紙芝居制作会社ができた。その制作会社が一方的に画家たちへの支払いの切り下げを通告してきたとき、画家たちは同盟して争議に入り、加太は指導者として大政翼賛会を利用しながら争議を勝利に導いた。
戦時中、友人知人の戦死の知らせが相ついだが、加太は疎開学童の慰問と文化指導の仕事などを与えられ、全国各地を回り、生き抜いた。
戦後、昭和21年に紙芝居は復活した。娯楽のない焼跡に拍子木の音が響くと、幼児から十代半ばの若者まで集まった。闇ルートで仕入れた景品のお菓子は、持って出ただけ売り切れた。
《22〜23年頃の紙芝居での私の人気と勢力は昭和初年に紙芝居が始まって以来類がなかった。「加太こうじと手のひらに書いて押しいただいてから拍子木をたたけば、売り上げが二割あがる」といわれるほどだった。全国の紙芝居屋五万人のうち二万人は私の作品を使っていた。》
《ヤミとインフレと食糧難の時代を、私は何ひとつ不自由なく過ごすことができた。》(『ふたりの昭和史』)
しかし20年代も末になり、世の中が回復してくるにしたがい、紙芝居業界は衰退に向かう。自動車が増えて街路で子供が遊ぶことが危険になり、駄菓子屋がテレビを置いて子供たちを引き付け、製菓会社のお菓子が出回り紙芝居屋の菓子をみすぼらしく見せた。多くの紙芝居業者が転廃業していく中で、加太こうじは紙芝居を捨てきれず、紙芝居の作画をする以外は焼酎を飲み、花札と麻雀とパチンコで日を送った。付き合いが普通だった友人たちは皆、彼を見はなした。
昭和34年のある日、ひとりの男が金を借りに来た。用事がある、と言って外出したが、その男はどこまでもついてきた。電車に乗り、知人がいれば話しかけてその男の無心を逃れようと考えたが、知り合いはいない。
ところが目の前に、「思想の科学」を持って腰かけている男がおり、加太はその男の顔を写真で知っていた。その男、鶴見俊輔は紙芝居に関心を持ち、加太こうじ本人には会わぬまま、調べたり書いたりしていたからである。
加太は自己紹介し、それがきっかけとなって昭和35年に中央公論社から『街の自叙伝』を出版し、以後、物書き業として生きていくことになる。
3.
『街の自叙伝』は、加太こうじの自叙伝であるが、彼が仕事としてその初期から終期までかかわった紙芝居という事業の、歴史の記述でもある。
紙芝居屋たちを束ねた全国各地のつわものたちの横顔が語られ、また紙芝居作家の名前が記録され、そのうちの幾人かはのちに有名になる。
山川惣治は別格だが、少年漫画に転身し「赤胴鈴之助」で一世を風靡した武内つなよし、貸本漫画の制作に転身し、「劇画」を創りだした白土三平や水木しげるや小島剛夕、といった名が見える。
しかし『自叙伝』を、紙芝居の歴史の資料であるにとどまらず、出色の読み物にしているのは、生き生きと語られる尾久の町の濃密な青春の交友である。
加太たちが高等小学校を卒業した昭和7年は、金解禁以降続く大不況のなかで労働争議や小作争議が頻発し、血盟団事件や五・一五事件が発生した年である。東京で生活することをあきらめた失業者が、家族を連れて線路沿いの道を徒歩で故郷へ帰る姿が、毎日のように見られた。
同級生たちは、師範学校に進学した一人をのぞき、工員、バスガール、食堂の給仕、株屋の小僧、駅の改札係、お茶くみの女事務員など様々な職業に就いた。しかし彼ら彼女らは仕事の傍ら集まっては、短歌の同人雑誌を出し、演劇の練習にはげみ、文化や芸術について語り合った。
加太の恋人は、秀子という名の同級生の女性だった。いっしょに短歌の同人誌を編集し、いっしょに演劇の練習をした。小柄で利口で愛らしく、大人びた歌を詠んだ。秀子も加太に思いを寄せていたが、結局結婚には至らず、他の男に嫁ぐ。しかし夫はやがて結核で亡くなる。昭和20年3月10日の東京大空襲で下町一帯が焼け、尾久の街も焼けた。秀子の消息は消えた。
加太は『街の自叙伝』を書きながら、本名で登場させるからには彼女の生死を確かめ、もし生きているなら承諾を得たいと考えた。方々に当たった末、彼女は生きて会津で蹄鉄屋に再婚しているとわかる。加太は長文の手紙を書いて自叙伝執筆のことを伝え、返事を急ぎ待つと書いて速達で送った。電報で返事がきた。
《イマヲヨリヨクイキントス」ムカシノユメニコダ ワラズ ゴ セイコウヲイノル」 ヒデコ》
加太は文章の末尾にこの電報を置き、自叙伝を書き上げた。
4
『街の自叙伝』の4年後に、加太は『ふたりの昭和史』(1964年)を山下肇と共同で執筆する。山下肇はドイツ文学者で、当時東大助教授。大正9年生まれで、加太より2歳若い。
加太と山下から、先祖の話をそれぞれ別の機会に聞いていたある出版社の社長が、ふたりの先祖が共通であることに気づき、引き合わせ、それが縁で共同して本を創ることになったのである。
ふたりは自分の生い立ちや少年期の思い出、戦時下の青春と戦後の生活を、交互に執筆する。山下肇は丸の内に通うサラリーマンの子供として生まれ、東京の目黒区で小学生時代を過ごし、それから同区内にあった七年制の府立高校の尋常科、高等科に進む。場末の尾久の街で育ち、高等小学校を出るとすぐに一家を養わなければならなかった加太とは対照的に、山下は父親の経済力の下、山の手の知識人としての十分な教育を受ける。
山下の学生生活も、けっして変化に乏しいわけではなく、多くの優れた教師や友人たちとの交流が語られる。少し優等生過ぎ、時代の思潮に安易に寄りかかった物言いも見られるが、それらも含め、東京の戦中派知識人の形成のされ方や教養の程度を示すひとつの材料を提供していると言える。
同時代の知識人の「自叙伝」としては、加藤周一(大正8年生まれ)の『羊の歌』(1968年)をはじめ、いくつも出されているが、山下の文章は中でもっとも時期の早いものであろう。
加太こうじは、『街の自叙伝』の後日談として、かっての恋人・秀子に再会した話を書いている。加太は所用で会津若松まで出かけた折に、郊外へ少し足を伸ばす。
《只見川の両岸の山は紅葉していた。しぐれが私のレインコートをぬらした。私は都会的な秀子がこの山の中でどんな奥さんになっているのかと思いながら只見川ぞいの道をあるいた。》
《学校の前までいくと鍛冶屋の鉄を打つ音がきこえた。気づかずにゆきすぎたのだが、今来た道にその音のする家があった。もどって少しはなれたところから表に面した仕事場を見ると槌をふるう男と、その男がきたえる鉄を器具でおさえている少年がいた。少年はこちらを見て男に仕事をやめさせて私に近づいてきた。それが秀子だった。セーターにズボンで頭を手ぬぐいで包んだ秀子は十二、三の少年に見えたのだった。さがす私よりも先にかの女は私を見つけたのである。》
槌を振るっていたのは夫の弟で、秀子が蹄鉄屋を切り回しているということだった。加太は、犬を連れて散歩に出ているという主人には会わず、30分ほどで家を出た。出がけに表札を見ると、秀子の名前が死別した夫の姓で出ていた。
《私は秀子の戦後の十数年が平穏でなかったことを知った。》
加太の抑制のきいた簡潔な記述は、青春の挽歌を叙するにふさわしい効果を上げている。
5
一度だけ加太こうじに会ったことがある。
昭和の終わりか平成の初め頃だったと思う。知人が「今のうちに加太こうじの話をテープに収めておこうと思うが、いっしょに行かないか」と私を誘った。知人の運転する車に乗り、三人で山梨県の温泉に行った。
道々、私は話題を探し、『ふたりの昭和史』のことも話題に出した。加太の書いた部分の方が、山下肇の書いた部分より面白かった、と感想を述べた。
「もう評価は(そういうことに)定まっているんです。」と、加太はつまらなそうに言った。「だから山下はその後、自分と一緒に仕事をすることにウンとは言わなかった……。」
宿に着くと、加太は温泉に浸かるでもなく、ウイスキーの瓶を取り出し、持参のカステラを肴にチビチビ呑みだした。やがて食事のお膳が出され、女将が来て一品ずつ料理の説明を始めたが、彼はウイスキーとカステラを続け、料理には手を付けなかった。
怪訝な顔をする女将に、私は廊下でなんとか言いつくろい、部屋に戻って加太にウイスキーとカステラでは、栄養に悪いのではないか、とやんわり言った。すると彼は、栄養とはなんですか、と突き放すように言った。にこやかな顔つきに似ず、強烈な自己主張をする人間を初めて経験し、私は半ば呆れ半ば圧倒された。
(おわり)
ARCHIVESに戻る