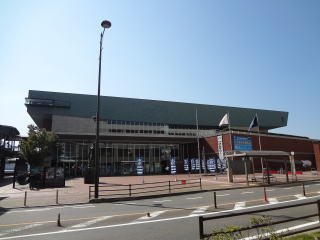鞆の浦・尾道・呉・広島の旅
【ブログ掲載:2015年10月23日~11月6日】
▼先週の土曜日、仲間といっしょに広島県の鞆の浦と尾道の街を歩いた。仲間とは、年に一度日本各地から集まりいっしょに旅行する友人たちで、メンバーは北海道から鹿児島まで散らばっている。すでに旅行を始めてから25年になり、4半世紀の間には亡くなった者も何人かおり、今では細君といっしょに参加する者も多い。
東京は雨がぱらつく曇天だったが、新幹線で西に移動するにつれて空は明るくなり、福山駅で降りると雲ひとつない青空だった。
福山駅前の「釣り人の像」の前で今年の参加者13人が落ち合い、鞆鉄バスに乗った。やがてバスの窓から穏やかな瀬戸の海が見え出し、ちょうど30分で鞆の浦に着いた。
まず坂本竜馬が宿泊したという枡屋清右衛門宅へ行った。坂本竜馬率いる海援隊が借り入れた「いろは丸」が、長崎で買い込んだ武器弾薬を大阪に運ぶ途中、紀州藩の持ち船と讃岐の沖で衝突して沈没する、という事件が起きた。枡屋清右衛門宅は、その談判をするために鞆の浦にやって来た龍馬や海援隊士が宿泊した屋敷なのだそうだ。
【龍馬たちは暗殺を恐れて階段のない部屋に泊まったという】
この事件の処理は長崎奉行に回されたが、紀州藩が政治的に威圧して問題を終わらせようとしたのに対し、龍馬は航海日誌や航路図により事実を確定し、「万国公法」によって解決することを主張、紀州藩に過ちを認めさせたという。
次に、福禅寺の対潮楼(たいちょうろう)へ行った。「風光明媚」を絵に描いたような景色を見ながら、座敷でしばし休憩。小島の点在する瀬戸内海は、絵になる構図にこと欠かないだろうが、ここの景色も評判どおり素晴らしい。
座敷の壁に、幕末の長崎で撮ったという写真が貼り出されていた。撮影者は日本のカメラマン第1号の上野彦馬、写真は外国人の大人と子供を中心に、集合した志士たち50名ほどが横3列に並んでいるものだが、驚かされるのはその顔ぶれである。「判明」したという一人ひとりの名を見ると、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允、高杉晋作、勝海舟、坂本龍馬……とオールスター・キャストである。感心して見ていると、説明役のオジサンが、ここに書かれた名前については異論がないわけではない、というようなことを婉曲に言い、一同、なあんだ、という顔になった。
港に出ると、「常夜灯」が見えた。鞆の浦の風景として、もっとも絵になる場所である。常夜灯の界隈には江戸期や明治期の建物がいくつも残っていて、風情ある街並みをつくっていた。
2時間ほどの街歩きでいいかげん疲れたあと、渡し船で仙酔島に渡り、国民宿舎「仙酔島」に泊まった。
▼翌日も晴天。朝食後、昨日の渡し船とバスに乗り、福山から尾道に移動した。
【宿泊した部屋の前は浜辺。夏には海水浴客で賑わうという。】
尾道駅構内にある観光案内所で地図をもらい、「古寺めぐりコース」を歩いた。コースの標識に従って持光寺、光明寺、宝土寺を通り、千光寺新道に出ると、道は急坂となり、まっすぐ石段を登る。まことに尾道は、寺と墓地、急坂と石段の街である。
五百羅漢の群像のある天寧寺まで歩き、ロープウエイで千光寺山の展望台に登った。尾道の街が眼下に広がり、その向こうの河のように見えるのは瀬戸の海(尾道水道)、向こう岸は向島(むかいしま)だと説明板にあった。
帰りは、尾道ゆかりの人物の句碑などが点在する「文学のこみち」を下り、千光寺に出、山を降りた。
昼食ののち、尾道駅で解散。筆者は電車で呉へ移動した。
呉は筆者にとって、最近まで映画「仁義なき戦い」の舞台というだけの街だったのだが、せっかく広島まで来たのに1泊で帰るのはもったいない、「どこぞ寄る所はないじゃろうか」と思い、立ち寄ることにしたのである。
ホテルに入ったのはすでに夕方に近かったので、「大和ミュージアム」に行くのは翌朝に回し、駅で手に入れた観光案内のビラで知った「潜水艦をもっとも間近に見られる」公園に、行ってみることにした。
駅前からバスに乗り、その名も「潜水隊前」というバス停で下車する。夕暮れの公園には、カメラを持った観光客が幾人も来ていた。目の前の海は海上自衛隊が占有しているようで、埠頭は立ち入り禁止となっていたが、潜水艦が4隻浮かんでいるのが見えた。
つづく
▼翌日も晴天。ホテルをチェックアウトしたあと尾道駅の周辺を散歩し、駅の南側の呉港に行った。
手前には江田島や広島港などへ行くフェリーボートの桟橋があり、斜め前方には造船所のクレーンが林立するのが見える。左手は海上自衛隊の駐屯地らしく、小型の艦船が係留された岩壁の横の広場で、隊員たちが駆け足や整列する姿が遠くに見えた。
9時過ぎに「大和ミュージアム」に入る。正式名称は「呉市海事歴史科学館」だが、これほど展示内容の情報を伝えない名称も珍しい。
「大和」は「戦艦大和」のことであり、戦艦大和に関する資料の展示とこの戦艦を生み出した呉市の歴史の解説が、「大和ミュージアム」の展示の2本柱である。2005年4月に開館したというから、今年はちょうど10年目に当たり、入場者は1000万人をすでに突破したという。この日は月曜日なのに、入館者でなかなかの賑わいだった。
展示室の入り口を入ると、太平洋戦争に関する簡単な解説をビデオで流していた。五百旗頭真(いおきべ・まこと)と半藤一利へのインタビューがその中に含まれており、「大和ミュージアム」の太平洋戦争への見方が、五百旗頭や半藤の歴史観に連なるものであることを示している。
明治政府は海軍の施設として横須賀に鎮守府を設置したが、西日本にも鎮守府を設けるべきだという声が高まり、選ばれたのが当時の呉村だった。呉には海軍工廠もつくられ、呉の街は海軍とともに発展した。戦艦大和もこの呉海軍工廠で建造された。
しかしそのため、太平洋戦争では米軍による徹底的な空襲の対象となり、街は廃墟と化した。現在呉の街を歩くと、道路は広く整然と整備されているのだが、これは空襲で壊滅したからこそ可能となったのだろう。
館内には戦艦大和の10分の1の模型が展示されていた。全長263メートル、最大幅38.9メートルの史上最大の戦艦は、日本がワシントン海軍軍縮条約を破棄したのち、対米戦争の主力として建造された。竣工したのは昭和16年12月16日、つまり対米宣戦布告の8日後だったが、建造を秘密にするため、竣工式は関係者だけでひっそりと行われたらしい。
▼呉港に停泊していた戦艦大和は昭和20年4月、片道の燃料だけを積んで沖縄に向け出発し、4月7日、米軍艦隊の爆撃機や潜水艦の猛攻を受け、屋久島の西方200㎞の地点で沈没した。乗員3332名中生存者は269名、竣工からわずか3年半だった。
戦艦大和と同型の戦艦が「武蔵」の名前で造られたことは、吉村昭の『戦艦武蔵』に詳細に記述されている。こちらは三菱の長崎造船所で大和よりも5カ月ほど遅く起工され、昭和17年8月に竣工した。そして昭和19年10月、レイテ沖海戦で米軍の空爆により沈没、竣工からわずか2年2か月だった。
太平洋戦争において艦隊同士の戦闘はほとんどなく、戦闘の主役となったのはそれまで補助兵力とされていた航空機や潜水艦だった。米艦の持たない口径46センチの巨大な砲を誇る大和と武蔵だったが、大艦巨砲主義の時代がすでに終わっていたことを、両戦艦の短い生涯が如実に語っている。
▼吉村昭の『戦艦武蔵』(単行本:昭和41年刊)について、一言記しておきたい。
吉村は友人・泉三太郎(ロシア文学者)から、昭和39年に「武蔵」の建造日誌の写真コピーを譲られた。吉村はいろいろな迷いを持ちつつも資料を読み込み、関係者に取材し、「武蔵」の建造準備から起工、進水、艤装、竣工を経てレイテ沖の海戦で沈没するまでを、作品にまとめた。
吉村昭は純文学の作家であり、この『戦艦武蔵』執筆中の昭和41年に小説「星への旅」で太宰治賞を受けたのだが、『戦艦武蔵』のあとは作風ががらりと変わった。綿密な取材と調査にもとづく「ノンフィクション」が、吉村の執筆する世界となった。
『戦艦武蔵』を書いたことが吉村にとって大きな事件であったことは、吉村が取材経過を記した『戦艦武蔵ノート』(単行本:昭和45年刊)からも読み取れる。調査を進めながら、「とうてい自分には書けないという意識と、文学に対する私の考えからも、書くべきではないという気持が強かった」と吉村は振り返るが、それでも彼は自分を鼓舞し、疲労困憊の末に書きあげた。
『戦艦武蔵』は、膨大な人力と資材を投入して造り上げた「海の城」が、想定した戦闘を行えぬまま1千名以上の人命とともに沈没するまでを、建造過程に重心を置いて描き切った「悲劇」である。徹底した事実調査と硬質な文体が、困難な主題の作品化を可能とした。
また、「戦艦大和」については奇跡的に生還した海軍少尉・吉田満が、その最期の出港から戦闘、沈没までを、叙事詩ともいうべき『戦艦大和ノ最期』に書き残している。
「大和」や「武蔵」に結晶した人間の営為は、これらの文学作品に描かれることで、はじめて記憶される形を持った。
(つづく)
▼「大和ミュージアム」を2時間ほど見たあと、隣接する「海上自衛隊呉資料館」へ行った。こちらの愛称は「てつのくじら館」と言い、現役を引退した本物の潜水艦をドンと正面に飾り、資料館の目印にすると同時に内部を公開している。潜水艦はくじらに似ているといえば、そう見えないこともない。
展示テーマの一つは、機雷の除去活動についてだった。太平洋戦争の末期、テニアン島を発進したB29は日本の艦船の航路を塞ぐために、太平洋、日本海、瀬戸内海に合わせて1万発以上の機雷をばら撒いたという。終戦後もそれらの機雷は残されたから、航路の安全のために機雷の除去、つまり「掃海」が欠かせず、海上自衛隊がその任務を担ってきた。
機雷はいろいろな形で進化しており、船がぶつかる衝撃で爆発するもの以外に、音や電波、磁気などに感応して爆発するものがあり、またアンカーとワイヤーでつながれて水中にある種類もあれば、海底に沈んでいる種類のものもある。したがって掃海の方法も、機雷の種類によって使い分けることになるが、日本の掃海技術は多くの経験を積んできたこともあって、きわめて高いらしい。
もうひとつの展示テーマは潜水艦だったが、こちらはたいした内容ではなかった。
資料館の正面に飾ってある潜水艦の中に入って見た。乗組員に割りあてられる空間はごくわずかなもので、低い天井の下に3段ベッドがしつらえてあったが、上と下のベッドの間は60㎝も空いていなかった。だが全長70~80mの潜水艦に70~80名の乗組員が乗り込み、さらに極めて多くの機能が詰め込まれるのだから、居住性がワリを食うのも仕方がないことなのだろう。
▼太平洋戦争で日本海軍の潜水艦は、大した戦果も挙げられずに終わった。
その原因は、海軍指導部が海上輸送の確保に関して関心が薄く、敵の海上交通路の破壊という分野に潜水艦を活用しなかったことにある、と言われる。
ドイツの潜水艦Uボート(Unterseeboot)は攻撃目標を敵の輸送船団に置き、敵の通商破壊に成果を上げた。ドイツ潜水部隊の総指揮官デーニッツは、戦争の帰趨はアメリカとヨーロッパを結ぶ大西洋のシーレーンを破壊できるかどうかにかかっていると確信していたし、チャーチルは一切の部門を挙げて対Uボート戦に力を集中した。
米国も日本の海上輸送路を破壊することに力を入れ、輸送船舶を沈めるために潜水艦を使い、日本の近海に機雷をばら撒いた。ところが日本の潜水艦は敵の海上交通路の破壊という目的には使われず、艦隊に随行して戦闘に参加することを目的に設計・建造されていたのである。
米国の太平洋艦隊司令官ニミッツ元帥は、次のように述べたという。
「古今の戦争史において、主要な武器が、その真の潜在威力を少しも把握理解されずに使用されたという稀有な例を求めるとすれば、それはまさに第二次大戦における日本の潜水艦の場合である。」(『日本海軍失敗の研究』鳥巣建之助 単行本1990年)
それでも日本の潜水艦の、潜水艦ならではの活躍がなかったわけではない。大戦の初期、インド洋からアフリカ大陸の南を回り、大西洋を北上し、英国の哨戒機が監視する中をドイツ占領下のフランスの港に入り、ドイツから「電波探信儀」を受け取るという離れ業を演じた潜水艦もあった。(『深海の使者』吉村昭 単行本1976年)
また、インド独立の運動家・スバス・チャンドラ・ボースを、亡命先のドイツから日本に招くことが計画された時も、潜水艦は活躍している。ボースはUボートに乗って密かにドイツを離れ、喜望峰の近くで日本の潜水艦に乗り換え、スマトラ沖の島まで運ばれた。ボースはそのあと海軍機で立川飛行場に飛び、「大東亜会議」(昭和18年11月)に「自由インド仮政府」の代表として出席した。
▼昼食に呉名物の「海自カレー」を食べてから、鉄道で広島へ行った。広島駅から路面電車に乗り、原爆ドームを見に行った。青空の下に多くの観光客が来ていて、原爆ドームの説明板を読んだり、カメラを向けたりしていた。
川に沿ってすこし歩き、橋を渡って平和記念公園に入り、それから平和記念資料館を見学した。原爆投下後の広島の街の写真や被災者の写真が何枚も掲げられ、また熱によってひん曲がった金具や熱風でボロボロになった衣服などが展示されていた。明るい緑色のジャンパーを着た「ボランティア」の人たちが、見学者に説明役を買って出ていた。
平和記念資料館で展示を見ながら、呉の「大和ミュージアム」で流していた太平洋戦争の解説ビデオの中の、半藤一利の言葉について考えた。そのビデオの中で半藤は、インタビューアーから「戦争を語り継ぐ」ことについて話しを向けられ、「………語り継ぐというと妙に英雄的になったりして………」と口ごもり、「それよりも若い人たちに、積極的に受け継いでもらいたい、歴史を勉強してもらいたい………」と語っていた。
半藤の言った「妙に英雄的になったりして………」の意味は、必ずしも明瞭ではないが、「体験を語ることはそれほど容易なことではない」という意味なら、よく分かる。そして歴史の記憶の伝承は、伝える側ではなく受け取る側の力に懸っている、という趣旨の発言は、問題の要点を突いていると思う。
「戦争を語り継ぐ」などと気楽に言う向きもあるが、聞く側が熱意をこめて問うことで、体験者も語ることができるのであり、その逆ではない。その体験を聞きたい、その経験を知りたいと欲する若い人々がいて初めて体験者は口を開き、経験は学ばれ、受け継がれるのだ。
半藤一利(1930年生まれ)は、昭和30年代に「週刊文春」の記者として多くの旧軍人たちの話を聞いて回り、記事を書いた。
秦郁彦(1932年生まれ)は学生時代から戦争の記録や体験記を読みまくり、旧軍人たちのもとを話を聞きに訪れている。
「大和ミュージアム」の館長・戸高一成(1948年生まれ)が語るところでは、戸高が大学卒業後に勤務した㈶史料調査会は、会長も上司も連合艦隊参謀という経歴の持ち主で、旧海軍士官のサロンのような職場だった。「毎日の昼食は太平洋戦史の講義のよう」であり、旧軍人や兵士たち数百人の話を聞く機会を得たことは、貴重な体験だったと彼は振り返っている。
半藤や秦や戸高が話を聞いた旧軍人たちはすでに世を去り、体験を聞き出した半藤や秦の世代も80歳代半ばになろうとしている。しかし幸いなことに、われわれは彼らが記録し、整理し、考察した歴史の記述を持っている。謙虚に学ぶ意欲のある者に歴史は十分開かれているのであり、イデオロギッシュな日本罪悪論にも惑わされず、「東京裁判史観」を批判すると称するイデオロギーにも誤魔化されない力を、それらは与えてくれる。
ARCHIVESに戻る